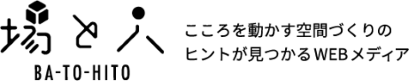SHARE
SHARE
店舗マーケティングは売上構成要素が重要!目的別に方法も解説
ショップ |
店舗で売上を上げるには、マーケティングが不可欠です。しかし、マーケティングがどのようなものかを理解するのは、やや難しいと感じて後回しにしている人もいるでしょう。この記事では、店舗マーケティングについて詳しく解説します。マーケティングのやり方や、成功のポイントもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
店舗マーケティングとは

そもそもマーケティングとは、企業活動において、商品やサービスの提供に関連する戦略全般のことです。これらのうち店舗マーケティングは、店舗の売上を伸ばすことを目的とした調査やリサーチ、商品企画・開発、販促活動など、店舗の運営に関わるマーケティング活動を指します。
インターネットやSNSを通してさまざまな情報が飛び交う現代において、店舗を出店し商品を陳列するだけでは、思うように売上を増やすことはできません。店舗もメーカーも、どうすれば顧客に店舗まで来てもらえるか、自社商品を選択してもらえるかを考える必要があります。店舗マーケティングは、そのための戦略であるともいえます。
店舗マーケティングのベースは売上構成要素
店舗マーケティングの基礎となるのが、売上構成要素です。売上構成要素には次の3つがあります。
来店客数
来店客数とは、特定の期間内に顧客が店舗を訪れた延べ回数です。来店客数が少なければ、どれだけ良い品揃えでも売上アップは見込めないことから、売上構成要素のなかでも重要なKPI(定量的指標)といわれています。
来店客数には、リピーターと新規顧客とがあります。さらに、いつも店に来てくれる固定客、まだ店に定着しておらず他店をメインに買い物をしているライトユーザー、以前は来店していたが店に来なくなった離反客など、細かく分類することが可能です。
購買率
購買率とは、来店客数に対して商品やサービスを購入した顧客の割合です。マーケティングにおいては、店舗の販売力を示す重要な指標といえます。具体的には、来店する顧客の購入意欲、また店舗の魅力度を反映する数字です。購買率は以下の式で計算できます。
購買率 = 購入客数 ÷ 来店客数
たとえば、200人来店して20人が購入すると、購買率は10%です。来店客数が少なくても、購買率を上げられれば売上の向上が期待できます。
平均客単価
平均客単価は、1人の顧客が1度に購入する平均金額を指します。平均客単価を出すには、次の式を用います。
平均客単価 = 店舗の売上高 ÷ 購入客数
たとえば、店舗の1か月の売上が500万円で購入客数が2,500人であれば、平均客単価は2,000円となります。平均客単価が上がれば、購入客数が変わらなくても売上高を向上させられるため、売上を上げる施策として平均客単価を向上させることも重要です。
来店客数を伸ばすための店舗マーケティング

ここでは、来店客数を伸ばすための店舗マーケティング施策について解説します。
オンラインによる新規顧客向けマーケティング
オンラインサービスを利用して新規顧客を開拓するには、次のようなマーケティング手法を用います。
- ホームページの運用
- ブログでの発信
- Web広告の活用
とりわけ実店舗では、Googleマップに店舗情報を登録することが重要です。顧客が店舗の営業時間や場所といった基本情報にアクセスしやすくなり、来店者を増やせる可能性があるでしょう。また、SNSでの情報発信も欠かせないマーケティング手法です。
オフラインによる新規顧客向けマーケティング
マーケティング手法は、オンラインが主流になりつつありますが、従来通りのオフラインにおけるマーケティングも無視できません。主なオフラインマーケティングの種類は、以下の通りです。
- チラシのポスティング
- フリーペーパーへの情報掲載
- ポスターの掲示
チラシはこれまで新聞の折込広告が主流でしたが、現在は新聞を購入している家庭が減っているため、個別のポスティングが望ましいでしょう。また、電車やバスの車内広告も、以前ほどではないにしろ一定の成果が見込めます。
リピーターを増やすためのマーケティング
リピーターを増やすための施策は、従来の紙ベースや会員カードからオンライン主体へと移行しています。たとえば、アプリを活用することで顧客の利便性が向上するとともに、顧客情報の収集も可能です。来店ポイントを付与する際もアプリの方がスムーズでしょう。
また、SNSの活用によって顧客とのコミュニケーション機会が増え、継続的な関心を引きやすくなります。さらに、アプリやSNSでのクーポン配布は、顧客の再来店を促す効果的な手法です。特に、クーポンに有効期限を設定することで、再来店までの期間を短縮できます。
購買率を上げるための店舗マーケティング

購買率を上げるための店舗マーケティング手法には、次のようなものがあります。
店内のレイアウトや陳列の見直し
顧客の購買率を上げるには、店内を回遊できるようなレイアウトが理想です。回遊性のないレイアウトになっていないか確認してみましょう。また、顧客が求める商品やサービスを探しやすくすれば、購買率は上がります。顧客視点に合わせてレイアウトや陳列を変更し、欲しいものが目に入りやすい売り場を目指しましょう。
商品やサービスの見直し
商品やサービスについて、ABC分析を行い、分析情報に合わせて商品やサービスを見直しましょう。ABC分析とは、たとえば「売上高」「在庫」といった特定の評価軸について、上位グループをA、中盤をB、下位グループをCとする評価方法です。評価結果を見て、顧客のニーズが高い商品やサービスを中心にラインナップを揃えれば、売上が伸びる可能性が高くなります。
商品やサービスの価格の見直し
ポジショニングマップを作成し、結果をもとに商品やサービスの価格を見直すことも効果的です。ポジショニングマップは、対象となる商品やサービスが、市場のなかでどのような立ち位置にいるかを示します。クオリティと価格のバランスを見ながら、他社の商品やサービスと比較しつつ適切な価格を設定しましょう。
平均客単価を高めるための店舗マーケティング

店舗マーケティングでは、平均客単価を高めることも重要です。効果的な施策には次のようなものがあります。
クロスセル
クロスセルは、商品を購入する顧客に対して、関連する商品を提案して購入に結びつける手法です。顧客がすでに商品の購入を決定している場合、その関連商品は、購入確率が高い傾向にあります。たとえば、カレールーを購入する顧客は、人参やジャガイモを購入する確率が高いといえるでしょう。
顧客のまとめ買いを促すと、平均客単価を上げやすくなる効果もあります。顧客側にとっては、まとめ買いすることで来店頻度を減らせるため、双方にとってメリットのある施策です。
アップセル
アップセルとは、顧客が希望している商品やサービスよりも、より高付加価値のハイクラス商品を提案し、購入してもらう販売手法です。たとえば、電化製品では追加機能を備えた上位機種を勧めることが該当します。
アップセルが成功すると、来店客数が増えなくても平均客単価が上がり、全体の売上を向上させることができます。しかし、顧客に対して上位商品のメリットをしっかり説明し、納得を得なければ購入にはつながりません。顧客が価値を感じる提案がポイントです。
店舗マーケティングを成功させるポイント

店舗マーケティングを成功させるには、次のポイントを押さえておきましょう。
仮説を立てる
マーケティングを行う際は、現状に至る原因について仮説を立てておくことで、手法が見えてくるケースがあります。たとえば、来店客数をマーケティングの課題とする場合は「入口が狭い」「広告宣伝が十分ではない」「ターゲットとエリア属性のミスマッチ」などを仮説として挙げておきます。
分析結果によって正しい仮説を絞り込みやすくなるため、仮説を複数立てておきましょう。その後、特定した課題に対して解決策を深掘りすることで、適切なマーケティング手段が明確になります。
オンラインを取り入れる
オンラインによる情報収集やコミュニケーションが主流になっているなかでは、マーケティングもオンラインの施策が欠かせません。実店舗では、オフラインの施策に重きを置いてしまいがちですが、顧客に足を運んでもらわなければならない実店舗こそ、広く情報を届けられるオンラインの施策が重要です。
WebサイトやSNSなどオンラインの施策が成功すれば、商圏外の顧客を獲得できる可能性も広がります。
マーケティングの効果測定を取り入れる
マーケティングを実施したら、効果を必ず測定することが重要です。効果測定によって、施策がどれだけ成果を上げたかを示すデータを収集・分析できます。データをもとに、成功した施策は次回以降のマーケティングに取り入れ、さらに改善を図ることが可能です。
効果測定の継続的な実施により、マーケティングの引き出しが増え、より多様な戦略を立てられるようになります。また、マーケティングにおいては、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回し、継続的な改善を行うことが成功へのポイントです。
まとめ
店舗マーケティングは、来店客数や購買率、平均客単価など、複数の視点から実施すると効果的です。課題を見つけたら、課題の原因がどこにあるのか仮説を立て、データを集めて分析を行いましょう。思うように来店客数が伸びない、購買率が上がらないといった場合、原因のひとつに「場」のミスマッチがあるのかもしれません。
丹青社は、多様な業界の空間づくりをワンストップでサポートしています。チェーンストア事業においては、パイオニアとしての競争優位を築いています。物販店や飲食店のデザイン・設計・施工をご検討の際は、ぜひ丹青社へご相談ください。
この記事を書いた人

株式会社丹青社
「こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル」として、店舗などの商業空間、博物館などの文化空間、展示会などのイベント空間等、人が行き交うさまざまな社会交流空間づくりの課題解決をおこなっています。

この記事を書いた人
株式会社丹青社