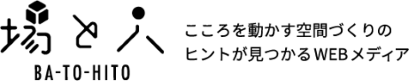SHARE
SHARE
ビジュアルマーチャンダイジング(VMD)とは?実践する方法を解説
ショップ |
店舗運営において効果的な施策のひとつが、「ビジュアルマーチャンダイジング(VMD)」です。ビジュアルマーチャンダイジングを実践すると、顧客の購買意欲を高められます。本記事では、ビジュアルマーチャンダイジングとは何か、取り組む方法やポイントなどを解説します。店舗の売上アップや、販売促進の方法を探している担当者はぜひ参考にしてください。
資料「店舗体験を最適化させる空間データ分析のはじめかた」を無料でダウンロードする
目次
ビジュアルマーチャンダイジング(VMD)とは?

まずは、ビジュアルマーチャンダイジングの意味や種類を確認しておきましょう。
ビジュアルマーチャンダイジングの意味
ビジュアルマーチャンダイジングとは、視覚的要素に重点を置いて売り場づくりをすることです。商品を見た顧客が、「この商品が欲しい」と思えるような売り場になるよう工夫します。英語表記の「Visual Merchandising」を略して、「VMD」とも呼ばれています。売上を上げるための店舗づくりを意味する、「マーチャンダイジング(MD)」の一種です。
マーチャンダイジングの種類
マーチャンダイジングの種類は、主に3つあります。
先述したビジュアルマーチャンダイジングに加えて、「クロスマーチャンダイジング(クロスMD)」と、「ライフスタイルマーチャンダイジング」です。
クロスマーチャンダイジングは、カテゴリーは異なるものの関連性のある商品を一緒に陳列し、ついで買いを促す方法です。ライフスタイルマーチャンダイジングは、ターゲット層のライフスタイルを考慮して取り扱う商品を選んだり、陳列したりします。
ビジュアルマーチャンダイジングとディスプレイの違い

視覚的要素を意識した店舗づくりというと、ディスプレイと同じような意味に感じるかもしれません。どちらも視覚に関連していますが、具体的な意味は異なります。
ディスプレイは商品を陳列したり売り場を装飾したりすることで、ビジュアルマーチャンダイジングは視覚的な効果による販売促進です。そのため、ディスプレイはビジュアルマーチャンダイジングに含まれます。
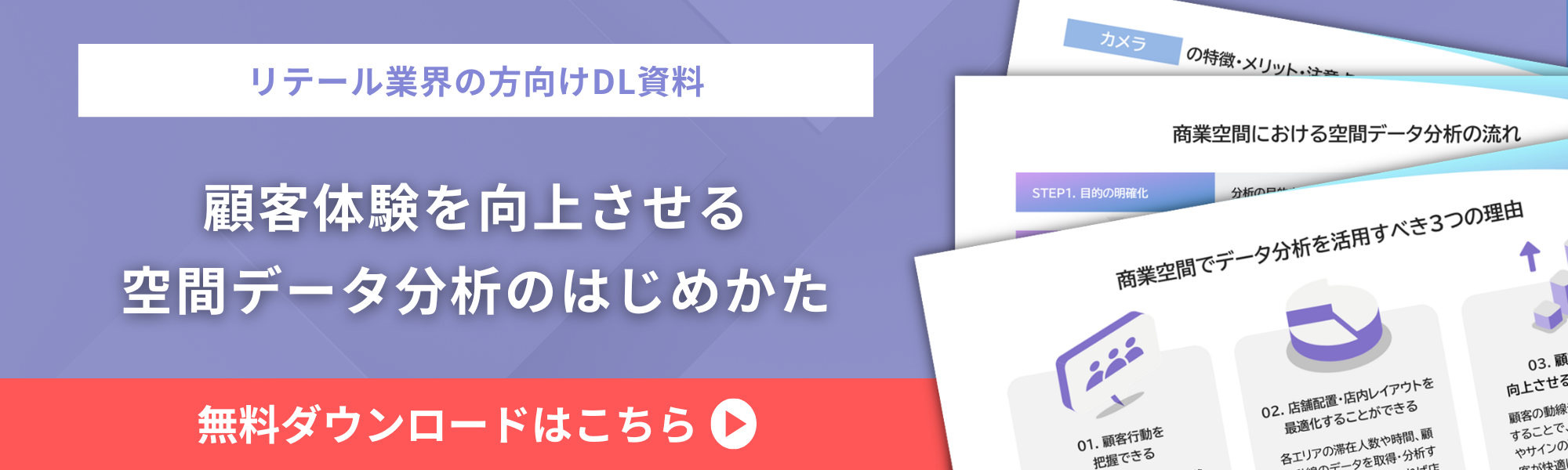
ビジュアルマーチャンダイジングの要素
ビジュアルマーチャンダイジングは、3つの要素で構成されます。ここでは、1つずつ解説します。
ビジュアルプレゼンテーション(VP)
「ビジュアルプレゼンテーション(VP)」は、入口付近やショーウィンドウなど顧客の視界に入りやすいエリアで、ブランドのイメージやコンセプトを表現することです。店舗・売り場・オフィスなどの第一印象や、全体的な雰囲気を左右する要素です。
ブランドイメージを表現したり、トレンドや季節を意識して統一感のある演出をしたりすると、注目を集めやすくなります。
ポイント・オブ・セールス・プレゼンテーション(PP)
「ポイント・オブ・セールス・プレゼンテーション(PP)」は、特に売りたい商品に注目を集めて、顧客の購買意欲を高める演出をすることです。例えば、マネキンにおすすめの商品を着用させて目立つ位置に展示したり、売りたい商品を店舗内の目立つ位置に大量に陳列したりします。顧客の視界に入りやすい位置で実施することが大切です。
アイテムプレゼンテーション(IP)
「アイテムプレゼンテーション(IP)」は、顧客が商品を比較したり、購入したいと思える商品を見つけやすくしたりする展示方法です。陳列棚やハンガーラックを活用し、見やすさ・選びやすさ・手に取りやすさを意識し、展示することがポイントです。
カテゴリー別やカラー別、シーズン別に陳列する、どこにどの商品があるのかをわかりやすく表示するなどして工夫します。
ビジュアルマーチャンダイジングの効果
ビジュアルマーチャンダイジングを実施すると、顧客に商品の魅力が伝わりやすくなり売上アップが期待できます。また、見やすく・選びやすく・手に取りやすい展示になっていることで、楽しみながら買い物ができ、顧客満足度もアップします。コンセプトやブランドのイメージが明確に伝わり、ブランドイメージを向上させることも可能です。
資料「店舗体験を最適化させる空間データ分析のはじめかた」を無料でダウンロードする
ビジュアルマーチャンダイジングに取り組む方法

ビジュアルマーチャンダイジングは、どのように取り組めばよいのでしょうか。ここでは、具体的に取り組む方法を解説します。
動線設計で購買プロセスを考慮する
動線設計を行う際は、AIDMAのフレームワークを利用して、顧客が商品を購入するまでにどのようなプロセスを踏むのか考慮します。
AIDMAとは、顧客が商品・サービスの存在を知ってから、購入するまでのプロセスのことです。頭文字のアルファベットは、「Attention(注意)」「Interest(関心)」「Desire(欲求)」「Memory(記憶)」「Action(行動)」を意味します。
視覚で顧客の注意を引く、興味を持ってもらう、購買意欲を高める、印象に残す、実際に購入してもらう、というように段階ごとに施策を検討しましょう。
陳列方法を商品の特性に合わせる
商品のサイズ感や形状、価格帯など、商品の特性に応じて陳列方法を変化させます。ゴールデンライン(ゴールデンゾーン)を活用しながら、美しい配置になるように規則正しく陳列しましょう。
ゴールデンラインとは、陳列棚のなかでも特に視認率が高く、顧客が商品を手に取りやすいとされるエリアのことです。ゴールデンラインに商品を陳列すると、購買意欲を向上させるといわれています。
振り返り・ブラッシュアップを繰り返す
新たな施策を実行した後は、振り返りとブラッシュアップを繰り返します。商品を購入した顧客の属性や購買履歴、課題や顧客のニーズなど、購買行動に関するデータを収集・分析しましょう。顧客の購買行動のデータを分析することで、戦略的な販売ができるようになります。課題や改善できる点がある場合は、ブラッシュアップをしていきます。
ビジュアルマーチャンダイジングにおけるポイント

ビジュアルマーチャンダイジングを実施する際は、意識したいポイントが3つあります。
ビジュアルに統一感を持たせる
ビジュアルに統一感を持たせて、ブランドやアイデンティティを表現することが大切です。統一感がないと、ブランドのコンセプトが伝わらないからです。
例えば、品質にこだわった大人向けの家具を販売している店舗の場合は、照明や内装を落ち着いた雰囲気にするなど、商品と店内のイメージを統一させます。統一感を持たせるためにも、コンセプトをしっかり決めてから取り掛かりましょう。
ディスプレイの基本法則を意識する
商品を魅力的に見せるディスプレイには、3つの基本法則があります。基本法則は、「商品をシメントリー(左右対称)に並べる」「目立たせたい商品は規則性を持って繰り返し並べる」「サイズや形が異なる商品はトライアングル(三角形)に配置する」です。基本法則に沿ったディスプレイを意識すると、顧客の視線を惹きつけやすくなります。
顧客視点で考える
顧客の気持ちになって考えることも重要です。顧客が商品を探しやすいレイアウト・動線になっているか、商品は手が届きやすい範囲に配置されているかなどです。ターゲットが子どもであれば陳列棚を低くする、どこに何かあるのかが一目でわかるようにするなど工夫します。また、季節や客層を意識して、顧客が欲しいと思えるような商品を販売することもポイントです。
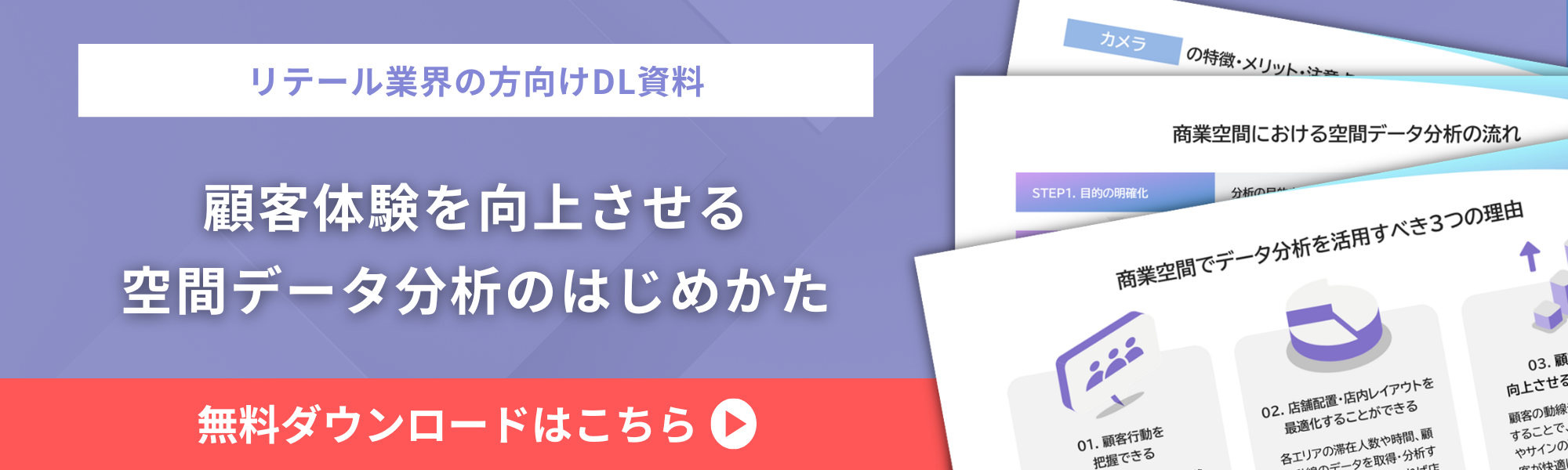
ビジュアルマーチャンダイジングが活用される業界
ビジュアルマーチャンダイジングは、スーパーマーケットや書店、アパレル、コスメショップなど、さまざまな業界で活用されています。さらに、インテリアショップやカーディーラーなど、小売業全般で効果が期待できます。売上アップを目指す際は、ビジュアルマーチャンダイジングを活用しましょう。
ビジュアルマーチャンダイジングの例

ここで、ビジュアルマーチャンダイジングにより、効果が得られた具体的な例を紹介します。
書店の例
ある書店では、顧客から新刊が見つけづらいという意見が寄せられていました。そこで、新刊コーナーのPOPを設置します。さらに、店内の雰囲気に統一感を出し、顧客の印象に残りやすくするために、手書きのPOPを作成しました。その結果、顧客が新刊を見つけやすくなり、新刊に興味を持つ顧客も増えました。
アパレルショップの例
あるアパレルショップでは、アイテム別に商品を陳列していました。商品は探しやすいものの、おすすめアイテムを強調できなかったり、着用したときのイメージができなかったりする点が課題でした。
そこで、目玉となるアイテムをマネキンに着用させて、店舗の中央付近や出入口付近に展示します。その結果、着用したときのイメージがしやすくなり、おすすめアイテムの魅力もアピールできるようになりました。
資料「店舗体験を最適化させる空間データ分析のはじめかた」を無料でダウンロードする
まとめ
ビジュアルマーチャンダイジングは、顧客の視覚に訴えかけて売上アップを目指す方法です。実施する際は、顧客目線になって購買プロセスや陳列方法を考慮し、ブラッシュアップと分析を繰り返していくことが大切です。小売業全般で活用できるため、ぜひ取り入れてみましょう。
丹青社は、多様な業界の空間づくりをワンストップでサポートしています。チェーンストア事業においては、パイオニアとしての競争優位を築いています。物販店や飲食店のデザイン・設計・施工をご検討の際は、ぜひ丹青社へご相談ください。
この記事を書いた人

株式会社丹青社
「こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル」として、店舗などの商業空間、博物館などの文化空間、展示会などのイベント空間等、人が行き交うさまざまな社会交流空間づくりの課題解決をおこなっています。

この記事を書いた人
株式会社丹青社