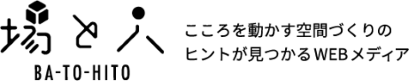SHARE
SHARE
都市は、“つくる”から“変える”へ|サステナブルな未来をかたちにする3つの挑戦
サステナビリティ |
コンクリートとガラスに囲まれた街で暮らすのが当たり前になった現代、本当にこのままでいいのか?という問いが、世界中で静かに広がりつつあります。気候変動やエネルギー問題、自然との共生など、多くの課題が私たちの生活に影響を与え始めている今こそ、「都市のかたち」を見直す時期なのかもしれません。
そんな中で登場したのが、持続可能性を軸にデザインされた新しい複合施設たち。都市に「やさしさ」と「強さ」を同時に宿すにはどうすればいいのか? その問いに対して、本気で答えを見出そうとする3つの場所を紹介します。
資料「丹青社が推進する内装の木質化」を無料でダウンロードする
目次
1. 木材で都市を再構築
「Stockholm Wood City」(スウェーデン)

Illustration: Atrium Ljungberg / Henning Larsen
スウェーデンのストックホルム郊外、Sickla地区で進行中の「Stockholm Wood City」は、総面積25万平方メートルに住宅2,000戸、オフィス7,000室を備える、世界最大規模の木造都市開発プロジェクトです。不動産開発会社「Atrium Ljungberg」が主導し、第一期工事は2025年に開始。住宅エリアは2027年までの完成を予定しており、その取り組みは既存の都市開発の常識を大きく塗り替える試みといえるでしょう。
最大の特長は、主構造材に環境負荷の低い集成材(マスティンバー)を採用している点にあります。この木材は耐火性・強度に優れ、工場でのプレファブ生産と現地組み立てが可能なため、建設工程における騒音や粉塵の発生を抑え、近隣への影響も最小限にとどめられます。加えて、建設スピードはコンクリート建築と比較して最大2倍。これにより、開発全体の投資効率も向上しています。

Illustration: Atrium Ljungberg / Henning Larsen

Illustration: Atrium Ljungberg / Henning Larsen
環境面では、建設・運用を通じたCO₂排出量の削減が期待され、都市全体でのカーボンフットプリントは従来のコンクリート構造より約40%低減できると試算。また、建材としての木がもつ調湿・空気清浄作用や心理的効果(ストレス軽減、集中力向上)などにより、居住者のウェルビーイングにも好影響を与えるとされています。
加えて、都市機能の設計も革新的。「Five-Minute City(5分都市)」というコンセプトのもと、住む・働く・学ぶ・買う・憩うといった日常の活動をすべて徒歩5分圏内で完結できるようにデザインされており、移動の効率化とCO₂排出の削減に大きく寄与する設計に。
さらに、地熱交換やソーラーパネル、蓄電システムの導入、生物多様性保全に向けたポケットパークの設置、既存樹木の保全、ハチの巣箱の導入など、都市全体が包括的に「環境と共に生きる」仕組みで構築されています。木造という素材選択から都市のマスタープランまで、すべてが持続可能性を前提にデザインされているのがこのプロジェクトの真髄。
Stockholm Wood Cityは、「自然素材を活かした高性能都市」の先駆けとして、ヨーロッパのみならず、世界中の都市づくりの新たな指針になっていく可能性を秘めているのではないでしょうか。
※その他の施設写真はスウェーデンの大手不動産会社「Atrium Ljungberg」のサイトからご覧いただけます。
● Stockholm Wood City /ストックホルム(スウェーデン) / オープン 2027年予定 / 総面積 250,000㎡ / 設計 Henning Larsen , White Arkitekter
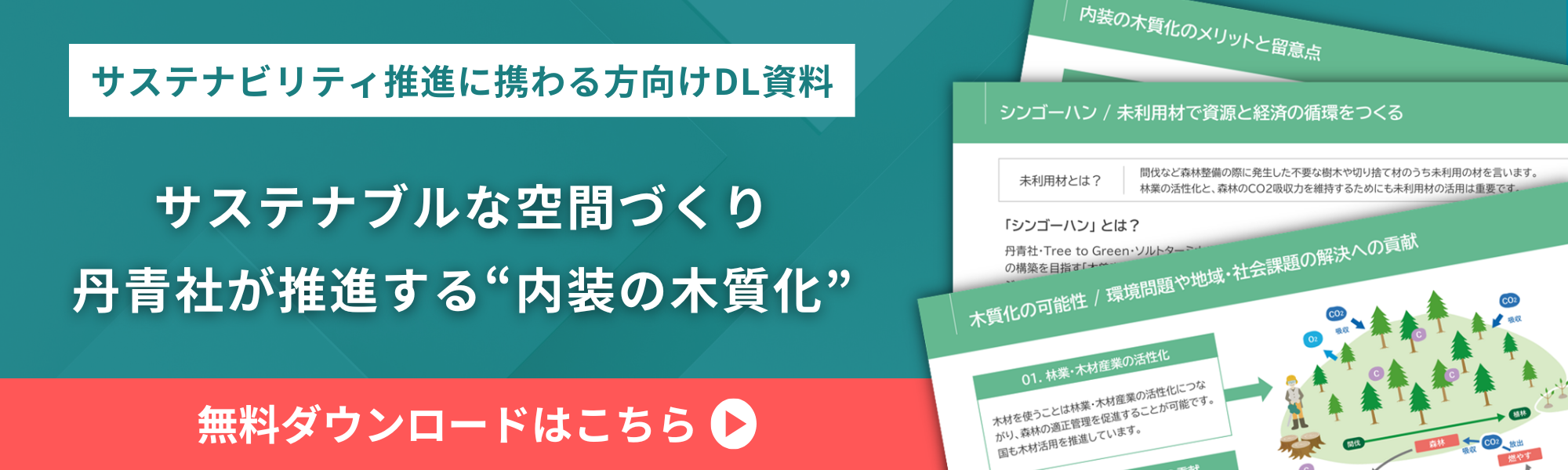
2. 体験設計が導くワークプレイスの再定義
「UnCommons」(アメリカ)

派手なネオンとカジノで知られるラスベガスですが、その郊外でまったく新しいタイプのコミュニティ「UnCommons」が誕生しました。ここは単なる開発プロジェクトではなく、都市の機能と人々の感性を結びつける“ライフスタイル型ワークプレイス”として構想された複合施設であり、全米でも注目される事例となっています。
開発総面積は約16ヘクタール。50万平方フィートを超えるオフィススペースに加え、9万平方フィート以上の商業空間、そして、最終的には830戸を超える住宅が建設される予定。2025年4月時点で、オフィス入居率はすでに93%、商業施設も90%契約済と、極めて高い市場評価を獲得しています。これほどのスピードで稼働率が上昇する背景には、「人が集まりたくなる設計思想」があります。


UnCommonsは、従来の画一的なオフィスとは一線を画し、働く場所を「体験の場」に変えるアプローチを採用。高速Wi-Fiと日除け付きの屋外コモンスペース、定期的に開催されるカルチャーイベント、地元との連携を活かした食のバリエーション。こうした要素が、在宅勤務に慣れた人々の「わざわざ行きたい理由」になっているようです。
飲食店はどれもラスベガス初上陸レベルのクオリティ。ステーキからパスタ、メキシコ料理まで、地元と世界の味がミックスされたラインナップで、UnCommons自体が食と文化の交差点としても機能。これにより、企業ワーカーだけでなく、地域住民や観光客との自然な接点が生まれ、都市としての持続力が高まっているというわけです。
住宅エリアでは、職住融合を前提とした設計がなされており、空間と健康とウェルビーイングに焦点をあてた評価システム「WELL認証」を意識した空調・通風システム、非接触型インターフェース、健康支援設計なども導入済み。UnCommonsは、都市の経済価値・文化価値・環境性能を三位一体で再構成しようとするモデルケースであり、都市の競争力を高めたい他地域にとっても重要な示唆を与えています。
※その他の施設写真はこちらからご覧いただけます。
● UnCommons /ラスベガス(アメリカ) / オープン 2023年 / 総面積 約160,000㎡ / 設計 Gensler , 開発元 Matter Real Estate Group
3. 空港跡地が再生する次世代型スマートシティ
「The Ellinikon」(ギリシャ)

かつてアテネの空の玄関口だった旧国際空港。その広大な跡地に建設されているのが、「The Ellinikon」と名付けられた次世代型スマートシティです。総開発面積は620万平方メートルを超え、国家規模の再生事業としてもヨーロッパ随一の規模。総投資額は80億ユーロに達し、最終的には85,000人以上の雇用創出が見込まれています。
このプロジェクトの中核には、生活に必要な機能を15分圏内に集約する「15分都市」のコンセプトがあります。住居、オフィス、商業、教育、医療、レジャーといった都市機能を効率的に配置することで、住民のQOLを高めながら、交通量と環境負荷の低減も同時に実現する戦略的な都市設計と言えるでしょう。
建設資材には、スイスの建築資材メーカー「Holcim」社による低炭素型の建材群(ECOPlanetセメント、ECOPactコンクリート、DYNAMax超高性能コンクリート)を全面的に活用。プロジェクト全体の構造物の90%以上で採用されており、建設段階でのCO₂排出量削減に大きく貢献するとともに、耐久性と循環性の両立が図られ、ライフサイクルコストの最適化も期待されています。


シンボルタワーである「リビエラ・タワー」は地中海地域で最も高い高層住宅となり、自然共生を前提に設計されたバイオフィリックデザインを採用。Foster + Partnersによる設計で、建物の環境性能を評価するLEED Goldプレ認証を取得するなど、国際水準のサステナブル建築が具現化されています。
また、Ellinikon Parkでは、300万株の植物と3万本超の樹木を導入し、地域の緑地面積を倍増させると同時に、生態系回復にも取り組んでいます。1.3kmの地下トンネルを含むスマートインフラ整備、アクセシビリティ重視の施設設計、障害者向けビルの導入など、持続可能性と包摂性が両立した都市像を提示しています。
The Ellinikonは、過去のインフラを活かしつつ未来の都市像を描く、まさに「再生の最前線」に立つプロジェクト。単なる再開発にとどまらず、都市の再生・経済・文化・環境を統合的に設計するモデルとして、今後の欧州都市政策や不動産投資のひとつの基準になると見られています。
※その他の施設写真はこちらからご覧いただけます。
● The Ellinikon /アテネ(ギリシャ) / オープン 2027年予定 / 総面積 約6,200,000㎡ / 設計 Foster + Partners(リビエラ・タワー), Kengo Kuma and Associates(リビエラ・ガレリア) , Bjarke Ingels Group(集合住宅群)ほか
資料「丹青社が推進する内装の木質化」を無料でダウンロードする
サステナブルな街づくりは、“問い直すこと”から始まる
今回紹介した3つのプロジェクトに共通しているのは、「環境にやさしい街」をつくるだけじゃない、という視点です。むしろその先にあるのは、暮らす人・働く人にとっての新しい選択肢をつくること。つまり、「こういう暮らし方・働き方もできるんだ」と気づかせてくれる都市ではないでしょうか。
Stockholm Wood Cityでは、スウェーデンの森林資源を最大限に活かしながら、建設速度や省エネ性能を含めたトータルバリューで従来構造を凌駕する成果が見込まれています。UnCommonsは、企業誘致や住民定着、都市ブランディングに貢献する“選ばれる場所づくり”の実践例であり、ポストコロナの都市設計を先取りしています。そしてThe Ellinikonは、国家規模の再生プロジェクトとして、インフラ・緑地・住宅・商業・観光を多軸で統合するフラッグシップケース。
今や都市開発において、「サステナブルであること」は付加価値ではなく前提条件。ESG投資やカーボンプライシング、グリーンインフラ・ファンドなどの台頭により、開発計画の初期段階から環境・社会インパクトの設計が求められる時代に突入しています。
これからの都市は、環境性能だけでなく、生活者の選択肢として納得感のある体験を提供できるかどうかが問われます。都市のサステナビリティとは、技術でも制度でもなく、人々の暮らしの質をどう保証できるかの総合的な挑戦ではないでしょうか。
都市をつくることは、未来の経済・文化・社会の在り方を設計すること。いま、私たちが見ているのは、単なる建築やインフラの話ではなく、「人がどのように生きるか」を問い直す、根本的な変化なのかもしれません。
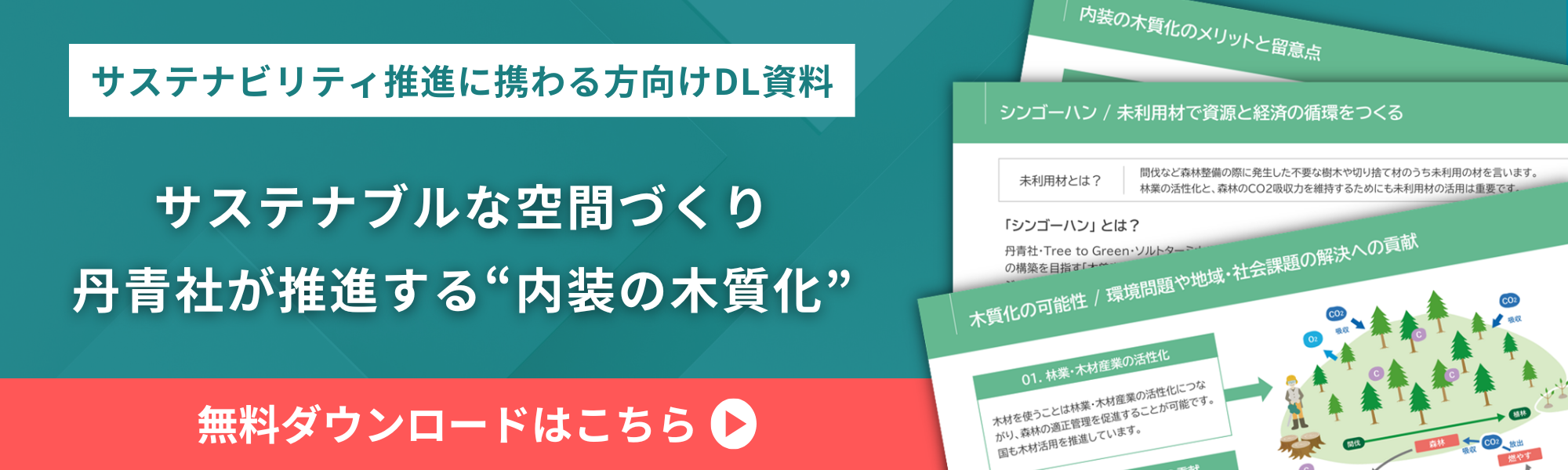
この記事を書いた人

株式会社丹青社
「こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル」として、店舗などの商業空間、博物館などの文化空間、展示会などのイベント空間等、人が行き交うさまざまな社会交流空間づくりの課題解決をおこなっています。

この記事を書いた人
株式会社丹青社