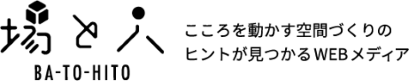SHARE
SHARE
サステナブルオフィス最新事例に見るウェルビーイング、環境配慮と経済性の交点
サステナビリティ |
サステナブルオフィスとはどのようなものでしょうか。省エネルギー、CO2削減、ペーパーレスやリサイクル。そして、ウェルビーイングのための緑化やラウンジスペースなど、その対応方法は多岐にわたります。
オフィスのサステナビリティ対応において、インテリアは何ができるでしょうか?その最新事例として、丹青社の名古屋支店と関西支店のリニューアルを紹介します。内装・空間づくりの会社が、どのようにサステナブルなオフィスづくりを進めたのか。自社のオフィスだからこそできる実験や挑戦を含めてその取り組みを追いました。

資料「サステナブルなオフィスづくりのポイント」を無料でダウンロードする
目次
オフィスへのサステナビリティ導入の背景と趣旨
今回のオフィスリニューアルの背景について、丹青社のサステナブル経営推進室・吉岡絵里さんに聞きました。
「2025年8月1日に『丹青社グループ ウェルビーイング経営方針』を発表しました。サステナビリティを実現し働く幸せを向上させる取り組みの一環です。従業員の多彩な個性と創造力を最重要の経営資源と位置付けており、その土台に、従業員一人ひとりの心身の健康があると考えています。
この前段として、創業100年の未来を考えた『私たちの未来ビジョン2046』を2024年に策定しました。サステナビリティは、その重要な要素の一つです。続けて『丹青社グループ サステナビリティ方針』を制定し、全社で様々な取り組みが進んでいます」

名古屋支店は2024年4月にBCP(事業継続計画)対策として最新のビルへ移転。関西支店は2025年2月に増員計画への対応として、1フロアから2フロアに増床しました。経緯は違えど、いずれも一連のウェルビーイングやサステナビリティ対応をふまえたリニューアルです。

両支店のリニューアルを担当した丹青社の総務部・玉野剛志さんにプロジェクトを振り返ってもらいました。
「名古屋では廃棄衣料をアップサイクルした『PANECOⓇ(パネコ)』を導入しました。関西では、さらに古材を使うことに取り組みました。被災された能登の古材で大きなテーブルを作ったのですが、材自体の選定のためにデザイナーに現地まで行ってもらいました。単なる移転や増床ではニュースになりませんが、こうした取り組みがあると空間づくりの会社としてアピールもでき、苦労はありましたが良かったと思います」
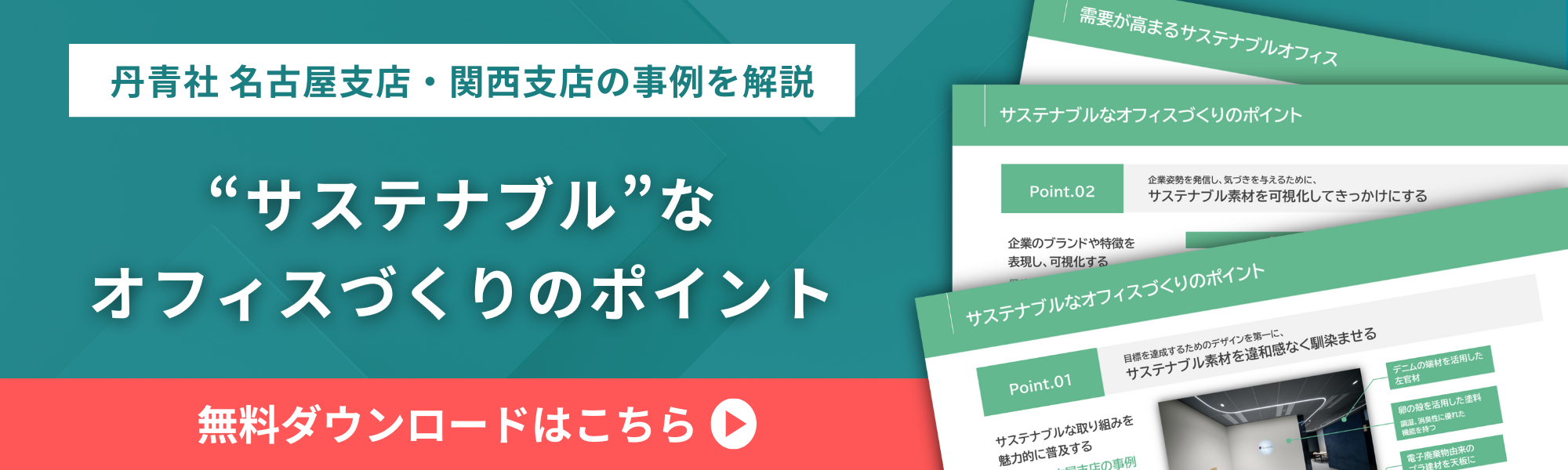
丹青社が実践するサステナブルな素材と手法
丹青社では社内で「サステナブル設計ガイドライン」を定め、チェックシートや社内アワードを活用して導入を推進するとともに、以下のようなサステナブルな素材や手法を用意しています。
廃棄衣料の利用「PANECOⓇ」

廃棄衣料をアップサイクルした建材で、壁材や造作家具の仕上げ材として活用できる。丹青社では、工事現場の作業着を利用してオリジナルの素材を作り利用している。
古材の活用「のと古材レスキュープロジェクト」
令和6年能登半島地震で被災し解体される建築物から古材や小道具を救い出し、再活用する取り組み。
廃棄物の利用「コーヒー豆」「卵の殻」「デニム」「陶器」
コーヒー豆のかす、卵の殻、デニムの端切れ、陶器などを粉砕し塗料として仕上げ材や左官アートのベース材として活用する。
他にも、カタログ廃番品の有効活用事業「4 earth」、100%マテリアルリサイクル可能な化粧板、木曽ヒノキを活用した合板、間伐材や小径木をはぎ合わせた突板、古民家の解体材の再利用「古木Ⓡ」などがあり、新たな取り組みも進行中とのことです。
サステナブルオフィス、空間デザインのポイント①:違和感なく馴染ませる/丹青社名古屋支店
デザインを担当した丹青社デザインセンターのワークプレイスデザインユニット・安元直紀さん(以下、安元さん)は「サステナブルな取り組みを魅力的に普及させていくことが、デザイナーとしての基本的な姿勢だと考えています」と言います。

「サステナブル素材に取り組む製造業の皆さんの思いをふまえ、どんな使い方があるのか?こうやって使ってみては?と考えて、空間デザインに取り入れていく。これが丹青社の使命だと思います」
一方で「押し売りにならないようにしたい」とも。
「クライアントの目標達成のために空間をデザインするのが私たちの仕事です。サステナビリティは与件に無くても当たり前に考えるもの。今回は、本社と支店のブランドイメージを揃えたいというクライアント(経営・総務)の意向を受けて、丹青社本社のラウンジスペース『クリエイティブミーツ』の雰囲気をイメージしてデザインしました。その上で、違和感なくサステナブル素材が取り入れられた空間となることを目指しました」

サステナブル素材についての経験値を積むための挑戦も行っています。「アップボーンレザー」という、革製品の製造過程における端材を粉砕し再形成した再生レザー。本物のレザーでは不可能な継ぎ目のない長尺な材が作れるというメリットがあります。その特徴を活かして会議室の大きなテーブルの天板に使っています。

「製造して頂いた協力会社さんからは『耐久性など保証が難しい』という話を頂きましたが、今回は施主が自社ですから、思い切って試しました。自らのオフィスで実験することで知見も溜まりますし、社内のサステナビリティ意識の醸成にもつながります」
資料「サステナブルなオフィスづくりのポイント」を無料でダウンロードする
サステナブルオフィス、空間デザインのポイント②:可視化してきっかけにする/丹青社関西支店
デザインを担当したのは丹青社デザインセンターのワークプレイスデザインユニット・那須野純一さん(以下、那須野さん)。

「新しいフロアをどう考えるか、支店長をはじめ、社員の皆さんとミーティングを重ね、考え方を共有し目的を設定しました。関西支店の魅力は、営業・設計・制作という3職種の距離が近いことです。新フロアを一つの職種だけが集まる場所にしてしまっては、それが損なわれます」
そこで導かれた新フロアのコンセプトが「Co.」です。「社内外のリアルコミュニケーションの場・共創の場(Co-creation)、環境と共生する循環社会を作ること(Co-existence)、丹青社の働き方発信の場(Co.,Ltd)という3つの意味を表します」

「既存フロアは社内のコミュニケーション活性化を狙うコアワークエリアとし、新フロアは、外部の方にも入って頂けるミーティングエリアと集中作業向け執務エリアで構成することとしました。これにより社員全員が新フロアを利用する動機を持つことができます」

「今の時代、サステナブル対応は当たり前のことですが、その姿勢を発信し気づきとなっていただくことも重要です。クライアントが将来的なオフィスを考える材料となるような、それが可視化できるオフィスづくりを目指しました」
「聞かれてもいないのに『この素材はサステナブルで…』と説明するのではなく、自然に話題となるように工夫したい。そこで、会議室の名前を『EGG』『DENIM』『COFFEE』としました。それぞれ卵・デニム・コーヒーの廃材や端材を利用した塗料やパネルを使っています。『変な名前だね』と話題になれば、それが糸口になります」

印象的だったサステナブル素材について聞きました。「やはり、能登の古材ですね。コスト、納期、加工性などが不透明だったので今回は実験的にセンターテーブルの天板に使うだけになりましたが、できあがりを見ると『全部、これにすれば良かった!』と思いました。やはり歴史、来歴がある素材はよいですね」

「PANECOⓇは想定以上にきれいに仕上がりました。もう少し粒度を粗くして、元の作業着の名残りが見えた方が良かったのかもしれません。ヴィンテージやアップサイクル、リサイクルの特徴や魅力を活かすさじ加減は難しいところです」
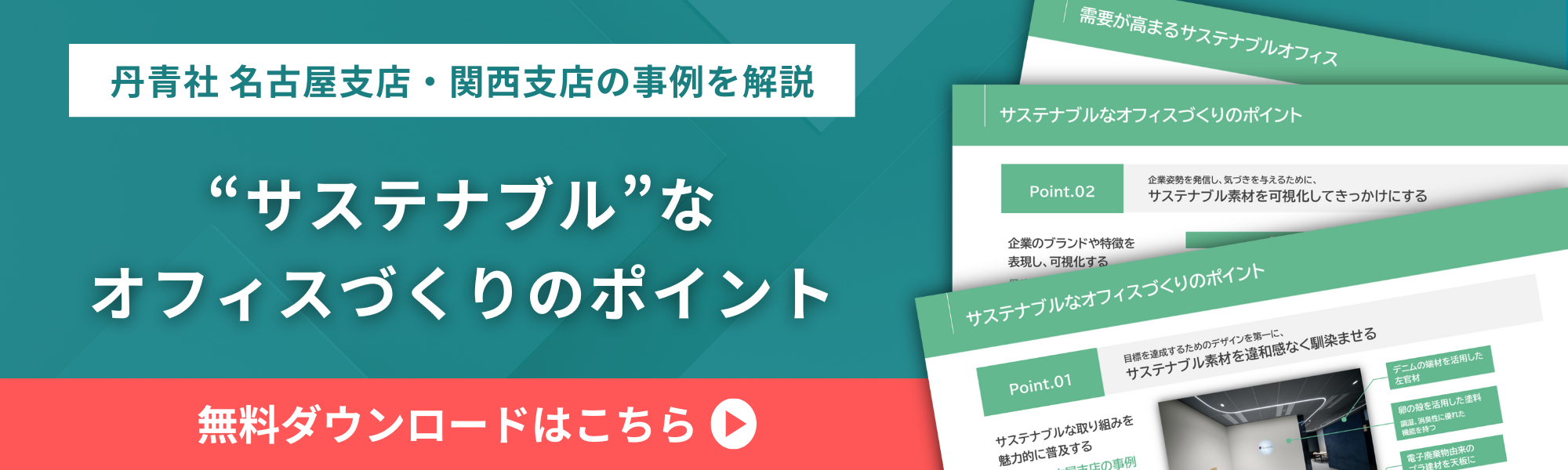
サステナブルオフィスはウェルビーイング・環境配慮と経済性が交わる場所
サステナブルオフィスについて、インテリアの観点から丹青社の2事例を紹介しました。サステナビリティへの対応を当然とした上で、目的達成のための空間づくりを考える基本姿勢が伝わってきます。
ただし、サステナビリティの社会実装には困難もあります。届け出や工事という時間の制約。不燃や難燃への対応、品質やコスト。そして、リサイクルやアップサイクルの素材を使いたくても、それらを加工する製造者や取り扱う施工者が少ないそうです。
一方、こうしたモノの環境配慮だけではなく、WELL認証のようなウェルビーイング対応もサステナブルオフィスには求められます。環境配慮、働きやすさ、そして経済性という、ともすると相反する条件をどのようにまとめあげて空間をつくるのか。簡単なことではないのですが、デザインの現場は前向きです。

安元さん「サステナビリティの導入は、クライアントの特徴を出すチャンスだと思います。たとえば、工場の廃材や端材を活用するなど、自分たちの事業活動を表現しやすい。環境配慮だけではなくてブランディングに直結するのがサステナブルオフィスなのでしょう。コストだけではない考え方があり得る領域です」

那須野さん「本来ならば、サステナブル素材だけで全て仕上げてもここまで魅力的に作れました、ということがやりたいです。まだまだ不燃認定素材は少ないですし、オフィスの家具も中古の手配は可能ですが、保証や在庫の問題などがあります。10年後、新品の材料を使うことが非常識になる時代が来るかもしれない。そんな時代を意識した先陣を切って行けたらと思います」
環境配慮だけではなくウェルビーイング、内部と外部へのブランディングなど様々な課題への対応策になるサステナブルオフィス。実現性、時間や費用という経済性も含めて自社のオフィスに落とし込んだ丹青社の挑戦は、サステナブルなオフィスづくりを検討する人にとって大きな参考となるでしょう。そして、これから実際に使い込まれていく状況も気になるところです。

この記事を書いた人

山崎泰 / 丹青社「場と人」編集長・ジャーナリスト
丹青研究所で商業施設の調査・企画に携わった後、1997年に丹青社の社内新規事業「Japan Design Net(JDN)」創業に参加。メディア「JDN」「登竜門」の編集長、コンテスト制作の事業化を経て2011年にJDN取締役。2025年、丹青社に移籍。デザインに関する取材執筆多数。趣味はサックス演奏。

この記事を書いた人
山崎泰 / 丹青社「場と人」編集長・ジャーナリスト