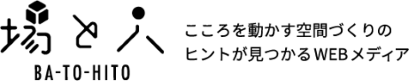SHARE
SHARE
Z世代は「大型商業施設」に何を求めている?インタビューから見えてきた意外なインサイトとは
まちづくり |
都心部には駅ビルやその周辺に様々な大型商業施設が新設され、郊外にもあらゆるコンセプトの大型ショッピングモールが増えている昨今。今後の消費や価値観をリードするZ世代(1990年代半ばから2010年代前半に生まれた世代)は、一体どのように商業施設を選び、足を運んでいるのでしょうか。SNSやメディアで取り上げられているようなトレンドやムーブメントは、確かなのでしょうか。
今回は3名のZ世代へのインタビューから、その本音やインサイトに迫りたいと思います。
資料「3つのキーワードから考える商業施設の未来」を無料でダウンロードする
目次
Case1. 「東京にいるときは新鮮さを、地元にいるときは寂れ感を求めている」(Aさん/23歳/男性/社会人1年目)
Aさんは大学進学をきっかけに東京へ4年住み、卒業後は海外留学の資金を貯めるために一時的に地元の新潟へ帰郷。東京に住んでいた学生時代に大型商業施設へ求めていたことと、地元で過ごしているときに大型商業施設へ求めていることの違いとは? そこからはZ世代らしいインサイトが読み解けた。

—— 学生時代、大型商業施設へ足を運ぶ機会はありましたか?
Aさん:何か予定があって渋谷などに行った際に、パルコやモディに立ち寄ることが多かったです。頻度は2週間に1回程度でしたが、ファッション関連や、レコードショップ、雑貨屋、フィギュアやおもちゃ系のお店が好きでした。ポップアップを見て回るのも好きです。田舎と違って、いつ行っても変化があることに驚きました。商品の入れ替わりや、毎回新しいポップアップがやっていることで新鮮な気持ちになれますし、再訪するきっかけになっていたと思います。
—— 都会の大型商業施設の好きなところと苦手なところを教えてください。
Aさん:好きなところは、ついでに立ち寄っただけでも常に新しい発見があるところ。苦手なところは、基本的に人混みにとてもストレスを感じるので、あまり頻繁には行けないところ。公園や広場のようなスペースもありますが、僕にとっては人がたくさんいることに変わりはないので、癒し空間だとは思えませんでした。SNSで人気の飲食店などがあることも知ってはいるんですが、並ぶのが嫌いなので行きませんし、オープンしたてで混雑しているような施設も避けていました。
—— 現在は一時的に地元の新潟に住んでいるそうですね。そちらでは大型商業施設へ足を運びますか?
Aさん:近所のモールには週に1回は必ず行きます。映画を見るついでに1人で行くことが多いですが、いつも空いているのでとにかく快適です。比較的新しい大型モールと、少し寂れたモールの2つがあるのですが、僕はつい寂れたほうによく行ってしまいます。おそらく人が少ないことが心地良いのだと思います。寂れたモールならではの、どこかやる気のない感じや雰囲気にエモさを感じるので気に入っていて、いつ行っても変わらないのが落ち着くのかもしれません。田舎はゆったりできると思われがちなんですが、実際には落ち着ける場所が少なくて、カフェとかも混んでるんですよ(笑)。あとはとにかくドラッグストアが多くて、あの明るすぎる店内の照明の感じが苦手で……。一方で東京は探せば落ち着ける場所もあるので、その中間があると良いのかもしれないですね。
【Aさんの3つのポイント!】
・都会型の商業施設ではポップアップが再訪きっかけに
・「人が少ない、混雑していない」ことが価値に転換
・「田舎にはZ世代が落ち着ける場所がない」と感じている
Aさんは「変化のある都会」と「変わらない地元」、相反する空間に惹かれながら、自分の“感情にフィットする空気感”を求めて商業施設を選んでいる。

Case2. 「週末は、家族や友だちと近所の商業施設へ。キーワードは “抜け感”」(Bさん/27歳/女性/社会人6年目)
Bさんは家族5人で東京に暮らしており、都心部の大型商業施設に友人と足を運ぶこともあれば、週末には二子玉川でゆったりした時間が過ごせるモールへ訪れることも多いのだとか。大型商業施設にトレンドを求めたいときと、リラックスを求めたいときの、それぞれのインサイトとは?

—— 普段、大型商業施設へ足を運ぶ機会はありますか?
Bさん:はい。都心の大きな施設は、友人と行くこともありますし、友人との待ち合わせまで少し時間があるときに立ち寄ってプレゼントを買ったりしますね。週末は都心に向かうことは少なく、家族と二子玉川ライズへよく行きます。ライズは雰囲気が落ち着いていて周りに自然もあるし、ほど良い抜け感が気に入っています。そこで映画を見たり、ショッピングしたり、本を読んだり、まったり過ごすのが最近のお気に入りです。家族とは、もっと郊外にあるアウトレットやモールに行くこともあります。
—— 「抜け感」についてもう少し詳しく聞かせてもらえますか?
Bさん:そうですね、シンプルに人口密度というか混雑していないことも重要なのですが、建物自体のセンスや、自然と調和しているところに心地良さを感じるのだと思います。特に目的がなくてもフラッと行きたくなりますし、ゆったりした時間が過ごせるのが私にとっては重要です。だいたいいつも午後から行って夕方くらいまで過ごして、そこで妹たちとご飯を食べることもありますし、そのまま自宅に帰ることもあります。
—— 大型商業施設の好きなところと苦手なところを教えてください。
Bさん:都心の大型商業施設に行くときは目新しさや新しい刺激を求めて行くことが多いので、期間限定のポップアップストアなどが好きです。苦手というほどではないのですが、最近はどこに行っても同じようなお店のラインナップになっていると感じることも多く、飽きているところがあるかもしれません。特に最近は人も多くて混雑していますしね。なのでやはり、何か目的があって行くというよりは、少し時間が空いたときに立ち寄る程度になっているのだと思います。
—— 最近気になっている大型商業施設はありますか?
Bさん:都内の新しい施設は、わりとオープンから日が浅いうちに、とりあえず1回は見に行くようにしています。あとは海外の施設も行きたいなと思っていて、SNSで見た韓国の現代百貨店やインスパイア モール、新世界プレミアムアウトレットなどが気になっています。旅行先だと行きたいお店の全てに立ち寄るのがスケジュール的に難しいので、人気のお店がまとまっている商業施設はありがたいですよね。
【Bさんの3つのポイント!】
・日常使いには自然と調和した「抜け感」のある施設が心地いい
・見覚えのあるチェーン店/系列店にはやや飽きている
・旅行先では「まとめ買い」をするために大型商業施設を重宝
Bさんにとって大型商業施設は、“目的地”というより“余白時間を心地よく過ごす場所”であり、日常と非日常をシームレスにつなぐ柔軟な目的地として選ばれている。
Case3. 「商業施設に求めるのは安心感。じゃないと疲れちゃう」(Cさん/23歳/女性/社会人2年目)
東京生まれ東京育ちのCさんは、いつどこの店舗に行っても「同じものがある」という安心感ゆえに、大型ショッピングモールが好きなのだとか。一方で、都心の若者向け商業施設にはあまり興味がなく、その理由が「疲れるから」とのこと。Cさんが頻繁に通いたくなる大型商業施設の条件と、そこから読み解けるインサイトを見ていきたい。

—— 普段、大型商業施設へ足を運ぶ機会はありますか?
Cさん:小さい頃から近所のアリオやイオンなどの商業施設が遊び場になっていて、いつも友人たちとショッピングやご飯、ゲームなどを楽しんできました。中高生の頃には一時的に渋谷や原宿などの都心に行くこともあったんですが、今は疲れちゃうのでほぼ行くことがなくなり、社会人になった今でも結局近所のアリオが一番落ち着くというか(笑)。
—— 「落ち着く」というのは、小さい頃から慣れ親しんでいる以外にも理由がありますか?
Cさん:ああいうショッピングモールが「画一的でつまらない」と感じる人もいると思うんですけど、私はむしろ逆で、いつも同じお店があることに安心感があるんです。お店のラインナップだけじゃなくて、トイレの場所や、休憩できるソファ、見覚えあるお店が並ぶフードコートなど、とにかく安心感があります。なので、いつも行っているショッピングモールのお店が変わってしまったりリニューアルすると、どこか寂しさみたいな感情も湧きます。一方で都会の新しくできた大型商業施設は迷子になってしまうし、行きたいお店になかなか辿り着けなくて息が詰まるというか、疲れてしまうんですよね……。
—— 「疲れるか疲れないか」が1つの基準になっているように感じました。他にも大型商業施設に期待していることはありますか?
Cさん:休憩できる場所があることにも繋がりますが、大型ショッピングモールの「誰にでも開かれているような雰囲気」が好きです。都心のオシャレな商業施設も行ってみたいとは思うのですが、どこかお客さんが限定されているような気がして、気遅れしてしまいます。だからこそ、刺激や変化はないかもしれないけど、いつ行っても安心感がある近所のショッピングモールが好きなのかもしれません。
【Cさんの3つのポイント!】
・ストレスなくトイレや休憩にアクセスできるインフラの優先設計
・施設や店舗の変化をネガティブに感じさせないホスピタリティやサポート
・誰でも、いつでも、どこでも安心して滞在できるユニバーサルな空間
Cさんにとって大型商業施設は、“変化”や“トレンド”よりも「いつも同じ」「誰でも受け入れてくれる」といった安心感が最も重要で、オシャレさよりも日常の拠り所としての居心地が選ばれる理由になっている。
資料「3つのキーワードから考える商業施設の未来」を無料でダウンロードする
まとめ
Z世代が何度も足を運びたくなるのは「=感情にやさしい場所」
今回のインタビューを通して見えてきたのは、Z世代にとって大型商業施設が「物を買う場所」から「自分にとってちょうどいい空間を見つける場所」へと変化していることではないでしょうか。もちろん物を購入するという体験(モノ消費)はそこに紐づいているものの、第一として捉えるべき価値観は、コト消費やイミ消費に変化しているようです。
たとえばAさんは、都会の商業施設に「新鮮さ」や「発見」を求めつつも、人混みは苦手で、地元の寂れたモールでは “変わらない”という体験に落ち着きを覚えています。そのときどきの感情に寄り添う空間を選び取る柔軟さが特徴的です。
【Aさんが求める空間づくりのヒント】
・専門家によってキュレーションされた希少性の高いポップアップ
・人との出会いやセレンディピティが生まれやすいカフェ&バー空間
・落ち着いた照明で、パーソナルスペースが保たれたリラックススペース
一方でBさんは、都心では刺激やトレンドを、週末には自然と調和した“抜け感”のあるモールで家族とのゆったりした時間を楽しむなど、目的に応じて過ごし方を切り替える「余白消費」的な感覚が見えてきます。
【Bさんが求める空間づくりのヒント】
・都会にいても自然を感じられる共生型の建築空間
・明確な目的がなくても足を運び家族と過ごしたくなる「余白」の演出
・旅先では、1度にまとめて話題のショップを周れる利便性
そしてCさんは、慣れ親しんだチェーン店や変わらない景色にこそ安心感を感じ「疲れない」「迷わない」ことを重要視しています。そこにはオシャレさよりも、いつでも自分を受け入れてくれる “開かれた空間” を好む傾向が見て取れました。
【Cさんが求める空間づくりのヒント】
・ストレスなくトイレや休憩にアクセスできるインフラの優先設計
・施設や店舗の変化をネガティブに感じさせないホスピタリティやサポート
・誰でも、いつでも、どこでも安心して滞在できるユニバーサルな空間
いかがでしたでしょうか。「Z世代」と言えど、その価値観をひとくくりにすることは難しく、インサイトから読み解けるヒントも三者三様となりました。一方でいくつかの共通点も見えてきており、新鮮さや刺激だけではなく「余白」や「親しみ」が求められる傾向は強いようです。

この記事を書いた人

株式会社丹青社
「こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル」として、店舗などの商業空間、博物館などの文化空間、展示会などのイベント空間等、人が行き交うさまざまな社会交流空間づくりの課題解決をおこなっています。

この記事を書いた人
株式会社丹青社