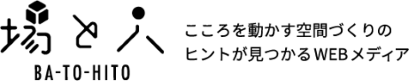SHARE
SHARE
会議室の稼働率を算出・確認するには?会議室の稼働率を適正にする方法も解説
ワークプレイス |
会議室の数と稼働率がかみ合わず、せっかくの会議室が有効活用できていないケースも多いのではないでしょうか。この記事では、稼働率の調べ方や、稼働率から分かる会議室の問題を解説します。加えて、会議室の稼働率を適正にするための方法や、会議室不足を解消する方法についてもまとめているので、オフィス運営の参考にしてください。
資料「会議室稼働率の適正化ロードマップ」を無料でダウンロードする
| 「働く場づくりに携わる方」へおすすめの資料 | |
|---|---|
会議室稼働率の適正化ロードマップ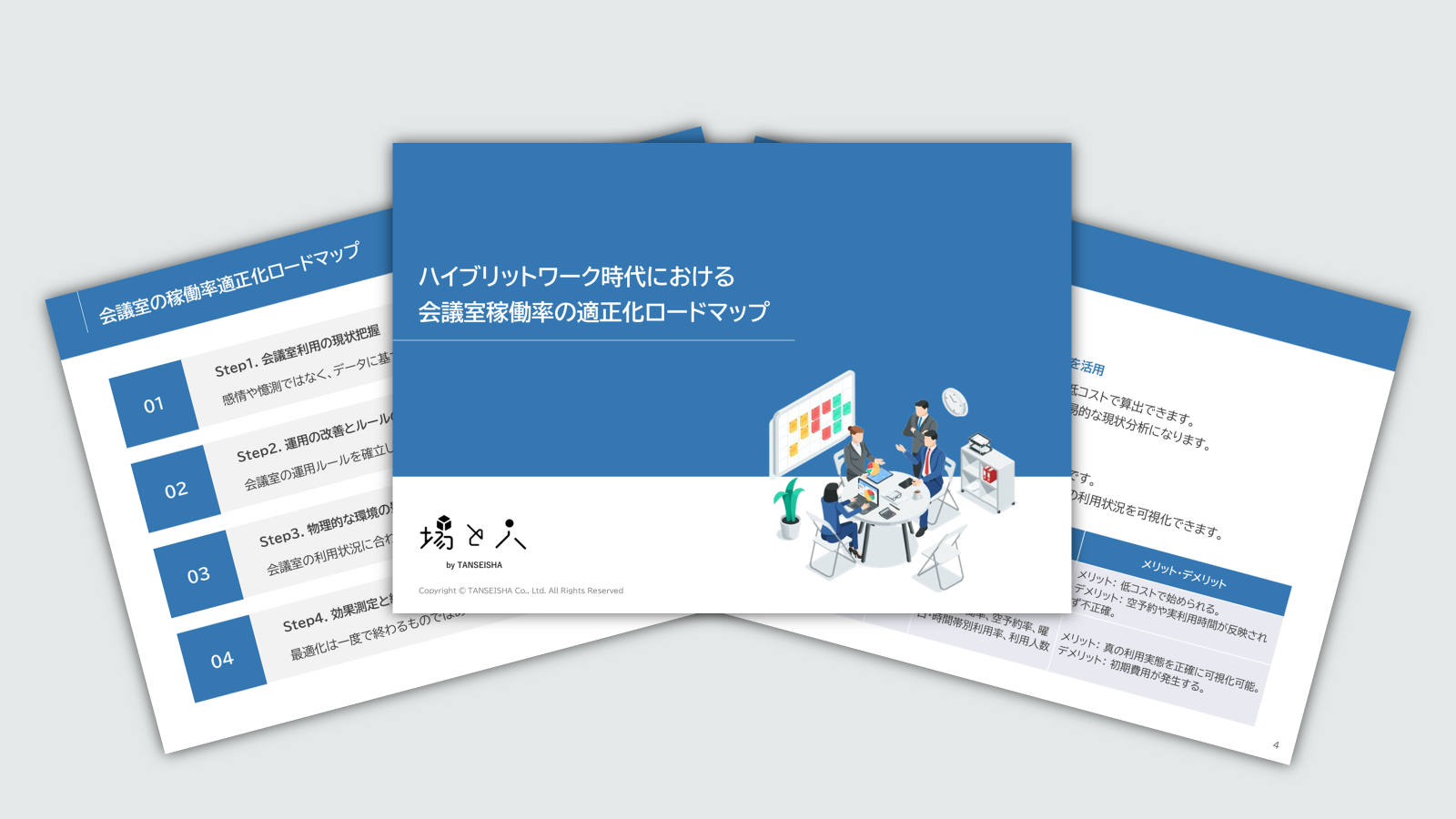 | ▼この資料でわかること ・会議室稼働率の基本 ・会議室稼働率の適正化ロードマップ ―Step1. 会議室利用の現状把握 ―Step2. 運用の改善とルールの確立 ―Step3. 物理的な環境の最適化 ―Step4. 効果測定と継続的な改善 >無料でダウンロードする |
オフィスを最適化する空間データ分析のはじめかた | ▼この資料でわかること ・オフィスで空間データ分析を活用すべき3つの理由 ・オフィスにおける空間データ分析の流れ ・空間データ分析でよくある失敗 ・各データ収集手法の解説 ・サービス紹介 >無料でダウンロードする |
Z3つのキーワードから紐解くZ世代の理想の職場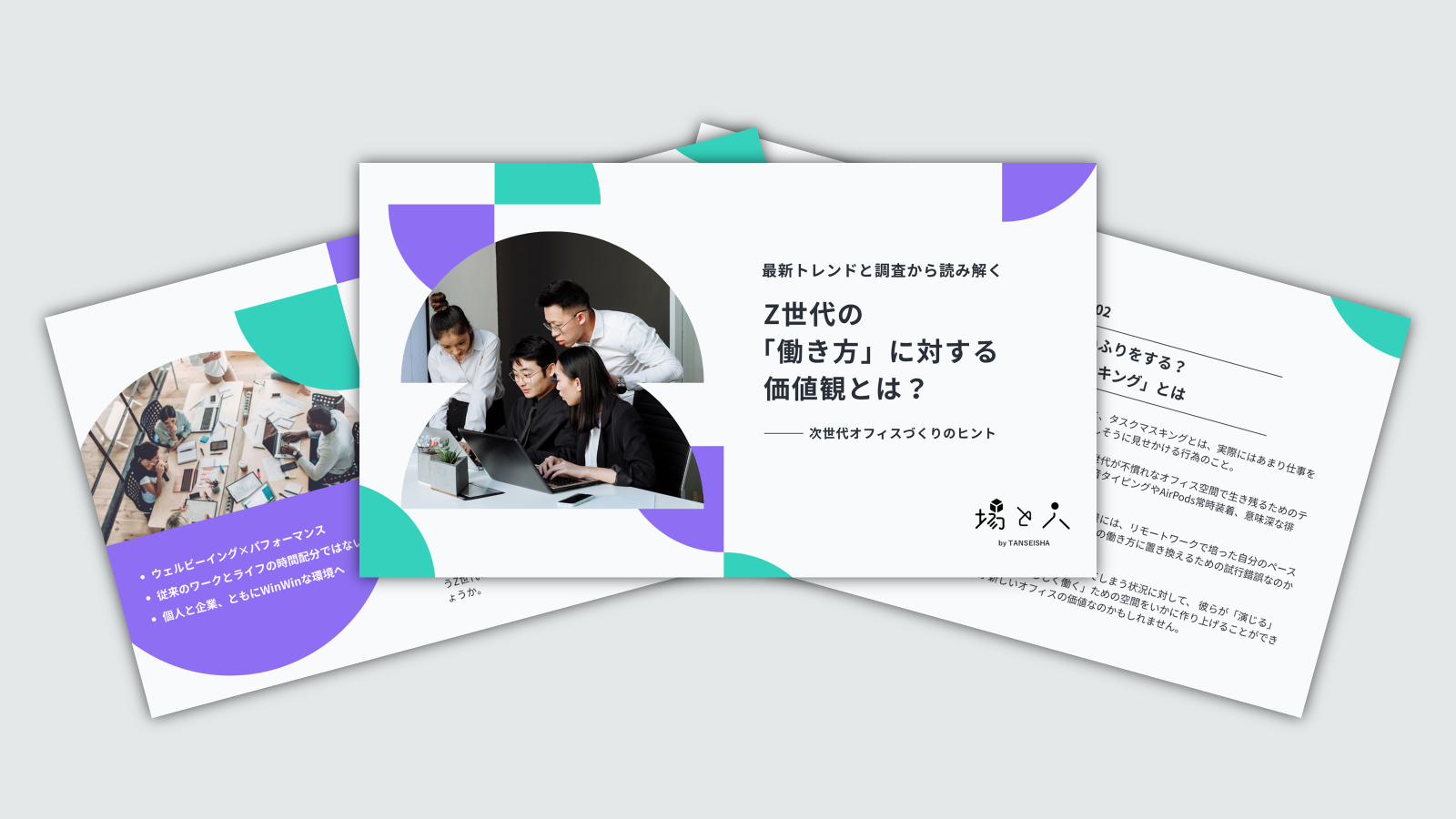 | ▼この資料でわかること ・Z世代と「働き方やオフィス」に関する注目の定量調査/データ ・“3つのキーワード”から紐解くZ世代の「働き方やオフィス」に対する価値観 >無料でダウンロードする |
目次
会議室の稼働率とは?

会議室の稼働率とは、会議室が利用できる時間に対し、実際に利用された時間を割合で示した数字です。計算式は、(稼働時間 ÷ 利用可能な時間) × 100で求められます。たとえば、利用可能な時間が12時間の会議室が、実際は9時間だけしか利用されなかった場合の稼働率は、(9 ÷ 12) × 100 = 75%となります。

会議室の適正稼働率とは?
会議室の稼働率は、高ければよいわけではありません。一般的に適正値は65~70%だとされています。それよりも低すぎると会議室のスペースが無駄になっている可能性があり、逆に高すぎても予約が取りづらい状態になるからです。
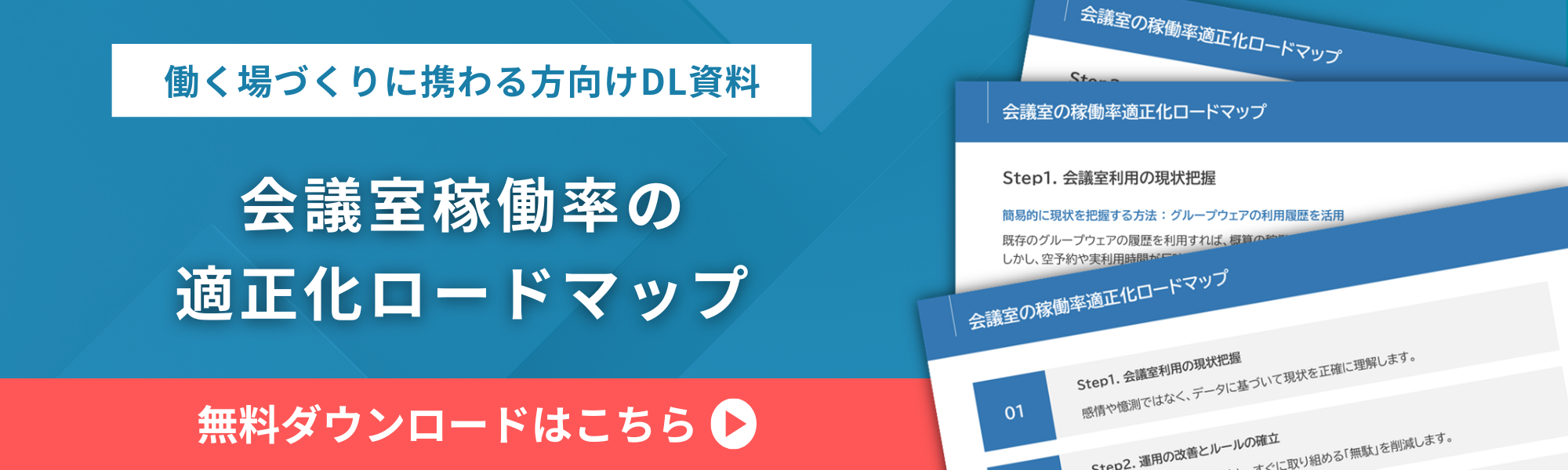
会議室の稼働率が高い場合のメリット・デメリット
稼働率が高い状態で会議室を運営できていると、スペースを有効に使えています。一方で、稼働率が高いゆえに使いたいときに使えないなど、従業員のストレスを招きかねない点はデメリットです。結果的に従業員からのクレームにつながる場合もあります。
会議室の稼働率が低い場合のメリット・デメリット
会議室の稼働率が低い場合のメリットは、空き状況に合わせてスケジュールを調整する必要がない点です。稼働率が低すぎるデメリットとしては、無駄なスペースとなっていることが挙げられます。稼働率が低い状態が続いている場合は、ほかの用途への活用を検討する必要があるでしょう。ほかの用途への活用を検討する際には、オフィスレイアウト全体の考え方を確認しておきましょう。
関連記事:オフィスレイアウトの基本やデスク配置パターンを解説【最新事例20選も紹介】
資料「会議室の稼働率適正化ロードマップ」を無料でダウンロードする
会議室の稼働率を確認する方法

稼働率の算出方法やメリット・デメリットが分かったところで、次は実際に使われている時間を確認してみましょう。確認方法は、主に以下の3つがあります。
利用履歴からの確認
会議室の利用にGoogleカレンダーなどを使っているのであれば、利用履歴をエクスポートして調べることが可能です。ただし、会議が早く終わったり、延長したりしている場合、正確な時間が反映されているとは限らないため注意する必要があります。
会議室予約システムによる確認
会議室予約システムとは、会議室の予約や入退室の管理を自動化するシステムです。会議室を使いたいタイミングで簡単に予約できるのはもちろん、利用状況を一覧で確認できる機能も備わっています。
利用時間を正確に把握しやすいうえ、蓄積したデータから利用状況の分析もできるため、会議運営の効率化が可能です。予約から一定時間過ぎても使われない場合はキャンセルできる機能や、終了時刻を知らせる機能がついているシステムもあります。
会議室IoTによる確認
人感センサーを使ったIoTシステムを活用すれば、会議室の空き状況や稼働率を「見える化」できます。管理者用にデータを収集できたり、利用者を確認できたりなど、会議室の利用状況が分かりやすくなるため、効率的な運用が可能です。

稼働率で分かる会議室の問題

稼働率を知っておくと、自社が抱える会議室の問題や従業員の不満が分かりやすくなります。以下で代表的な問題を解説します。
会議室の数
会議室の稼働率が高すぎる場合や、どの会議室も稼働率の高い状態が続いている場合は、そもそも会議室自体が足りていないことが考えられます。働き方改革の推進やコロナ禍を経て、以前よりWeb会議が実施されるようになり、会議数が増加している企業は少なくありません。
そのため、稼働率が高すぎる場合は、会議数や従業員数に対して会議室数が足りていないのかもしれません。会議室が空いていないと業務が非効率になったり、商談の機会を失ったりするリスクがあるため、注意が必要です。
会議室の面積
会議室を効率的に活用するためには、適切な広さも意識する必要があります。数名の会議やWeb会議で広い会議室を使うのは非効率ですし、参加者数に対して狭い会議室ではストレスを感じながらの会議になるでしょう。
大きなサイズの会議室を少ない人数で利用する場合は、1つの会議室を2つに分割すると空間に無駄がありません。逆に可動式パーテーションを取り払えば、広い会議室として使えるなど、レイアウトや面積を柔軟に変更できればニーズに応えやすくなります。
会議室のレイアウト
従業員が使いやすいと感じる会議室では稼働率が高く、使いにくく感じる会議室は稼働率が低くなる傾向があります。会議室の広さが変わらないにもかかわらず、稼働率に違いが出るようならば、座席やデスクのレイアウトによって使いやすさ・使いにくさがないか注目してみてください。
関連記事:会議室を活用する7種のレイアウトとは?参加人数に合わせた広さの目安なども解説
予約の取りづらさ
終了予定時刻を過ぎても終わっていない、逆に早く終わったにもかかわらず開放されていない、空予約が多いなどの原因があると、予約の取りづらさにつながります。予約方法が複雑だったり、会議室を探すのに手間がかかったりすると業務が非効率になり、商談の機会損失を生むリスクも高まるでしょう。会議や会議室利用のルールを徹底し、浸透させる必要もあります。
空予約
とりあえず会議室を押さえておきながら、実際には使わない「空予約」が多い場合、稼働率は高いにもかかわらず、実際の利用率は低いという現象が起きます。会議予約システムの機能を使って空予約を防いだり、ルールを徹底したりすることで空予約の防止につなげてください。
ダブルブッキング
予定を管理しきれていなければ、会議室を二重に予約してしまうダブルブッキングが起こりやすくなります。ホワイトボードに予定を書き込んだり、Excelで予定を管理したりする方法では、記入・入力漏れが起こりやすく、予約の取り直しなど余計な作業が増える可能性があります。会議室の利用が多い場合、アナログな管理方法は極力避けた方が無難でしょう。
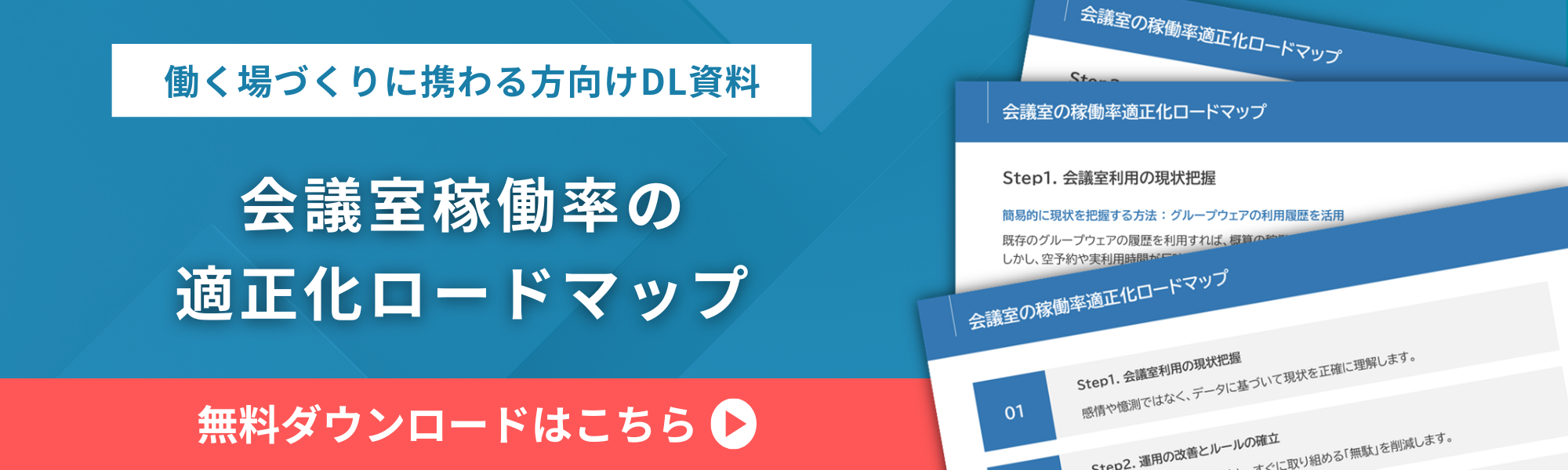
会議室の稼働率を適正にする方法

では、会議室の稼働率を上げるためには、どうすればよいのでしょうか。以下で4つの方法を挙げて解説します。
必要に応じた会議室数にする
どの会議室も常に稼働率が高いようならば、数が足りていないと判断できます。会議室の数が足りない場合は、会議室や会議スペースを増設することを検討しましょう。Web会議が多いようならば1人用の会議ブースを設置するなど、必要に応じた数やレイアウトにしてください。必ずしも個室である必要はなく、オープンスペースの設置も有効です。
会議室の面積やレイアウトを工夫する
稼働率を参考にしつつ、会議室の過不足を把握し、利用人数や目的によって適正な面積になるようにレイアウトを工夫しましょう。ミーティングスペースを新設するなど、レイアウトを変更することで会議室不足の解消につながるケースもあります。デッドスペースや空きスペースをパーテーションで仕切り、ミーティングスペースとして活用するのもおすすめです。
予約管理システムを導入する
予約管理システムを導入することで、稼働率の改善が期待できる場合もあります。特に会議や会議室の利用ルールが徹底されていないケース、空予約・ダブルブッキングが多いケースでは、管理がしやすくなるため効果的です。
会議の目的や会議室の使い方を従業員に理解してもらう
従業員に会議室やミーティングスペースの利用目的を意識してもらえるよう、再確認してもらう必要があります。たとえば、会議室は課題や問題についての議論や協議をする場としてはもちろん、意思や方針の決定、機密事項の話し合いなど、重要な話し合いをするのに適した場所です。
一方で、ミーティングスペースはアイデア出しや、情報・思考を共有するのに適しています。目的や利用人数に合わない会議で会議室を埋めてしまっていたり、稼働率を高めたりしていないかを認識してもらいましょう。
会議室不足を解消する方法

会議室が不足していると、業務に支障が出るかもしれません。そこで、会議室不足を解消する3つの方法を解説します。
会議室・ミーティングスペースを増設する
利用目的や人数、予約方法の再確認を経ても会議室が足りないようなら、増設を考える必要があります。広いスペースを仕切って2つにしたり、仕切りを外して広い会議室にしたりするなど、利用目的や稼働率を考慮して変更するのも効果的です。
貸し会議室などを利用する
スペースの新設が難しいのであれば、貸し会議室やコワーキングスペースの利用を検討してみてください。ただし、外部の会議室を利用する際は、セキュリティ面での安全が確保できる場所を利用するよう、周知徹底することが重要です。
会議自体の見直しを行う
会議室の稼働率が高すぎる場合は本当に実施する必要があるのか、会議自体の見直しが必要かもしれません。ただ定例化しているだけの会議や不必要な会議、時間の延長が常態化している会議などは、ルールの見直しを行うようにしてください。
資料「会議室稼働率の適正化ロードマップ」を無料でダウンロードする
まとめ
会議室の稼働率が適正でなければ、せっかくの会議室を有効活用できていないかもしれません。適正稼働率は65~70%であり、高すぎても低すぎても問題があります。稼働率から分かる課題や問題を明らかにし、稼働率を適正にすることが大事です。
丹青社は、多様な業界の空間づくりで培ったノウハウを活かし、柔軟かつ的確なオフィス空間をご提案します。現在のオフィスに課題を持つ方は、ぜひ丹青社へご相談ください。

| 「働く場づくりに携わる方」へおすすめの資料 | |
|---|---|
会議室稼働率の適正化ロードマップ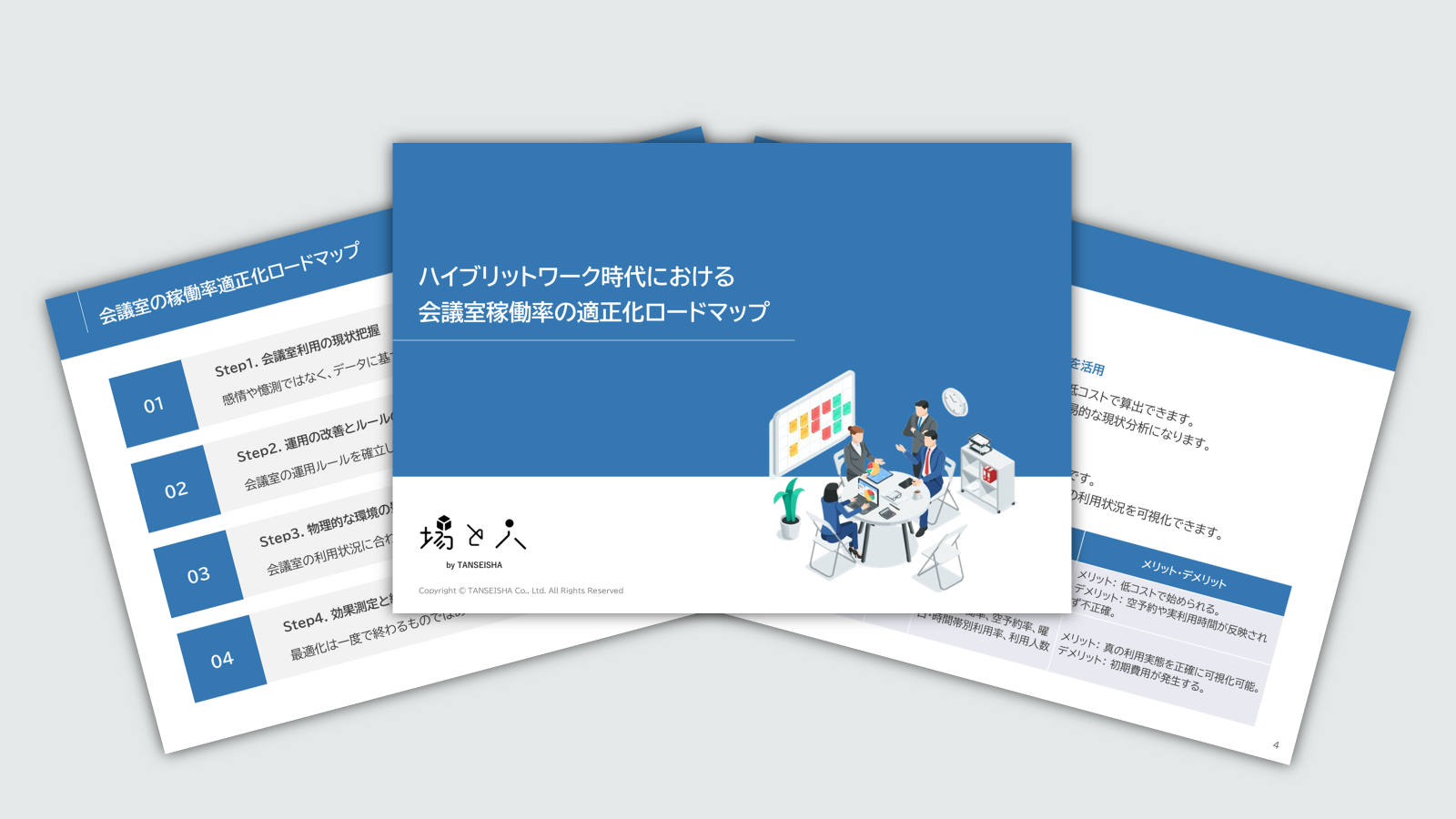 | ▼この資料でわかること ・会議室稼働率の基本 ・会議室稼働率の適正化ロードマップ ―Step1. 会議室利用の現状把握 ―Step2. 運用の改善とルールの確立 ―Step3. 物理的な環境の最適化 ―Step4. 効果測定と継続的な改善 >無料でダウンロードする |
オフィスを最適化する空間データ分析のはじめかた | ▼この資料でわかること ・オフィスで空間データ分析を活用すべき3つの理由 ・オフィスにおける空間データ分析の流れ ・空間データ分析でよくある失敗 ・各データ収集手法の解説 ・サービス紹介 >無料でダウンロードする |
Z3つのキーワードから紐解くZ世代の理想の職場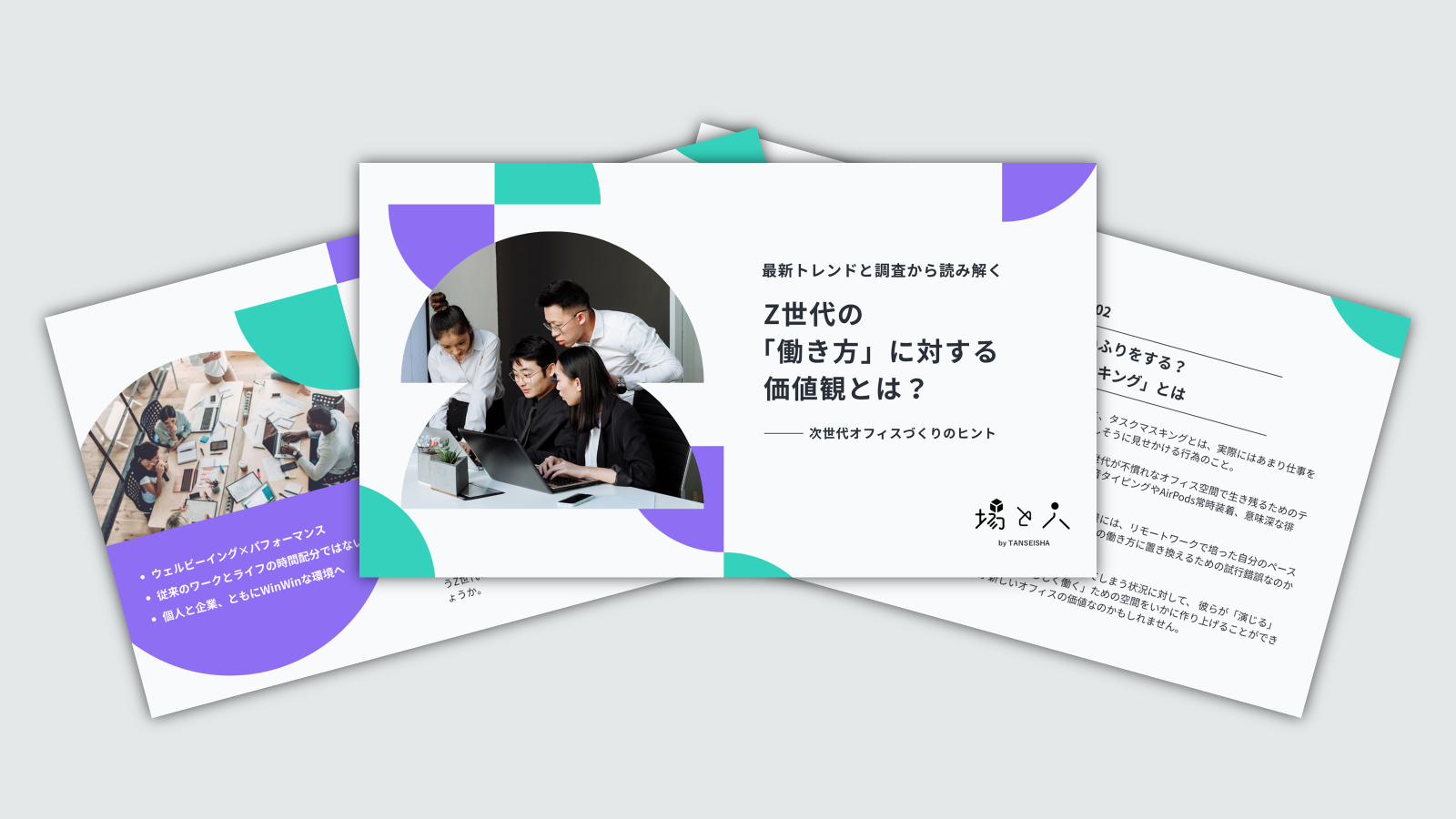 | ▼この資料でわかること ・Z世代と「働き方やオフィス」に関する注目の定量調査/データ ・“3つのキーワード”から紐解くZ世代の「働き方やオフィス」に対する価値観 >無料でダウンロードする |
この記事を書いた人

株式会社丹青社
「こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル」として、店舗などの商業空間、博物館などの文化空間、展示会などのイベント空間等、人が行き交うさまざまな社会交流空間づくりの課題解決をおこなっています。

この記事を書いた人
株式会社丹青社