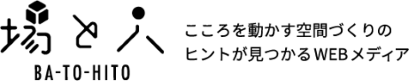SHARE
SHARE
オフィス回帰の原因とは?テレワークからオフィスへ、その転換点を探る
ワークプレイス |
新型コロナウイルスの流行は、働き方に大きな変化をもたらしました。そのひとつがテレワークの普及です。一方で、ウィズコロナ・アフターコロナ時代が到来したことで、オフィス回帰を進める企業も増加しています。
本記事では、オフィス回帰が起こっている原因や、オフィス回帰を推進する企業の特徴を解説します。テレワークが定着している企業との違いもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
資料「3つのキーワードから紐解くZ世代の理想の職場」を無料でダウンロードする
目次
オフィス回帰とは

オフィス回帰とは、テレワークを見直して出社回数を増やすことを指します。総務省の調査によると、テレワークを導入している企業は、下記のように推移しています。
| 2018年 | 19.1% |
| 2019年 | 20.2% |
| 2020年 | 47.5% |
| 2021年 | 51.9% |
| 2022年 | 51.7% |
| 2023年 | 49.9% |
新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年に急速に導入が進み、2021年にはテレワーク実施企業が半数を超えました。しかし、2021年をピークに実施企業は減少傾向にあり、2023年は50%をわずかに下回る結果となりました。この要因として考えられているのが、2023年に新型コロナウイルスが5類へ移行したことです。
東京都の調査においても、2023年4月にはテレワーク実施率が50%を切ったことが発表されています。これらの現状を踏まえて、企業にはオフィス回帰するかどうかの判断が求められています。
参考:令和6年版 情報通信白書|総務省
参考:テレワーク実施率調査結果 4月|東京都

オフィス回帰はなぜ起こっているのか

続いては、オフィス回帰が起こっている原因や背景を見ていきましょう。
コロナが落ち着いてきたから
オフィス回帰が起こっている理由として、新型コロナウイルスの5類移行に伴い、アフターコロナの時代になったことが挙げられます。テレワークの導入は、東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、計画的に進められたケースもありました。しかし、十分な準備ができない状態のまま、テレワークの実施に踏み切った企業も少なくなかったようです。
体制や設備が整っていないままテレワークを導入したことで「仕事の連携が取りづらい」「進捗が管理できない」といった問題が発生し、企業の業績にも大きなダメージを与えました。もちろん自社の課題を解決し、快適で生産性の高いテレワークを実現した企業も存在します。
しかし、テレワークにより業務効率が低下し、売上にも悪影響が出たような企業では、アフターコロナの時代となったことでオフィス回帰の動きが活発になりました。
対面の接触が重要であるから
「リモートでは対面でのコミュニケーションを超えることができない」と判断した企業は、オフィス回帰を選択した傾向にあります。人との接触が制限されたコロナ禍においては、ビジネスの打ち合わせの多くが、対面ではなくリモートへと切り替わりました。
リモートでの面談や会議は、相手の顔を見ながら話ができるものの「発言のタイミングが難しい」「スムーズに会話できない」といった課題があります。このような課題を解決するための手段として、対面での接触を重視する企業が増えています。社内の打ち合わせはリモート、クライアントとの商談は対面のように、目的に合わせて使い分けているケースも少なくありません。
業務の進捗を分かりやすくなるから
業務の進捗を把握しやすいところも、オフィス回帰が進む理由のひとつです。テレワークでは物理的な距離があるため、他の人の様子が分かりづらく、管理する側の負担も大きなものとなっていました。在席や勤怠を管理するシステムもあるものの、監視の意味合いが強いと従業員にとってもストレスを感じやすくなります。
一方で、オフィスに出社して自席で仕事をする状況であれば、それぞれの業務の進捗状況を把握することは容易です。気軽に相談もできるため、トラブルが発生した際も連携を取りながらスムーズな解決が目指せます。
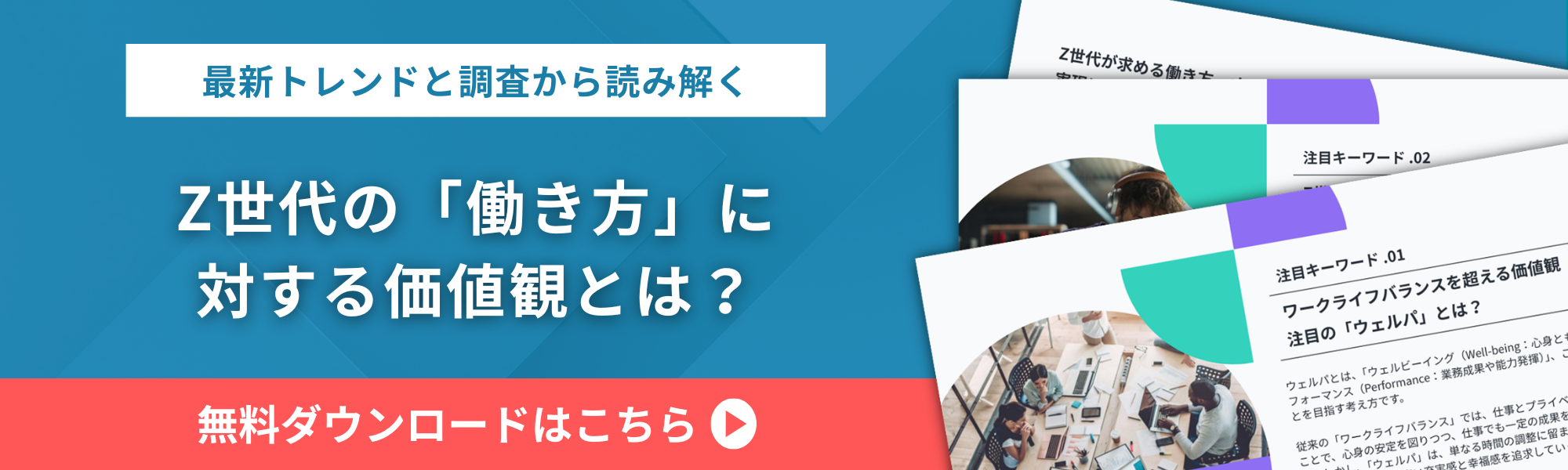
オフィス回帰を進める企業の特徴

オフィス回帰を進める企業には、共通した特徴があります。ここでは、主な3つの特徴について解説します。
イノベーションが生まれやすい環境作りを意識している
多くの企業は「クリエイティブな仕事」「イノベーションの創出」を大切にしています。テレワークでもクリエイティブな仕事はできるとはいえ、コミュニケーションの方法は限定的です。
オフィスで仕事をする場合は、雑談を通して新しいアイデアが生まれたり、思いがけない解決策が見つかったりすることも珍しくありません。革新的な技術を生み出し、事業を発展させてきた企業ほど、オフィス回帰を進める傾向が強くなっています。
対面のコミュニケーションの重視している
オフィス回帰を進める企業には「対面のコミュニケーションを重視している」といった特徴もあります。リモート会議は、細かなニュアンスが分かりにくかったり、ラフなディスカッションがやりにくかったりするなど、複数の課題が明らかになってきました。また、自宅で仕事をすることでプライベートとの境界が曖昧になりやすく「テレワーク疲れ」といった新たな問題も発生しています。
テレワークによりコスト削減や業務効率化を実現している企業でも、テレワーク疲れの状態に適切に対処できなければ、徐々に生産性は低下する恐れがあります。このような状態に効果的な対処法とされるのがオフィス回帰です。フルリモートで行える仕事であっても、週に数回出社することで運動不足も解消でき、心身を健康に保ちやすくなります。
従業員を正当に評価しようとしている
従業員の働いている姿が見えないテレワークでは、正当に評価されないケースも少なくありません。これは、部署やチームの評価者が従業員の成果に気づかないことが大きな要因です。たとえば、売上金額などの定量的な成果は把握しやすいでしょう。
一方で「陰ながら後輩の失敗をフォローしている」といった行動をしていても、評価者が目の当たりにしなければ正当な評価は得られません。このような定性的な評価項目、たとえば勤務態度や積極性などを適切に評価するために、従業員の働きぶりが見えるオフィス回帰を検討する企業も増えています。
テレワークが定着している企業の特徴

オフィス回帰が進む一方で、テレワークを継続していく意向を示している企業も数多く存在します。ここでは、テレワークが定着している企業の特徴を解説します。
働き方の自由度が高い
働き方の自由度が高い企業は、テレワーク継続の動きを見せています。テレワークの継続により、ワークライフバランスが充実し、従業員エンゲージメントも向上します。
「通勤時間が負担」「家族や友人との時間を確保したい」という従業員にとって、テレワークという働き方が選択できることは大きな魅力です。テレワークが定着することで、育児や介護との両立がしやすくなり、従業員の離職も防止できます。
単身赴任や転勤が少ない
完全在宅勤務に対応する企業では、単身赴任や転勤を伴わない働き方が実現できています。東京一極集中が深刻化するなかで、テレワークは「転職なき移住」を促進するためのキーワードともいえます。基本的に、テレワーカーが自主的に居住地を移転するのは自由です。
出社を前提としていないため、会社からの距離にかかわらず自分が希望する場所で働けます。このような働き方は、従業員の負担やストレス軽減にもつながり、健康経営にも役立ちます。
有能な人材を確保できている
テレワークを定着させている企業は、国内外から有能な人材を確保しやすい環境を整えています。テレワークで働く従業員は居住地に縛られることなく、自分のスキルやポテンシャルを最大限に発揮することが可能です。
企業にとっては多様な人材を活用できるメリットがあり、働き方の自由度が高まることで従業員のモチベーションも期待できます。このように、労使間双方のメリットを活かしていることも、テレワークが定着している企業の特徴といえます。
資料「3つのキーワードから紐解くZ世代の理想の職場」を無料でダウンロードする
オフィス回帰でもフリーアドレスを導入するケースが多い

オフィス回帰に伴い、ハイブリッドワークが増加しています。ハイブリッドワークとは、オフィス出社とテレワークを組み合わせた働き方です。ハイブリッドワークを採用することで、状況に応じて働く場所が選べるようになります。
また、限られたオフィススペースを効率よく活用するために、フリーアドレスを導入するケースも増えています。フリーアドレスを導入する際は、ワークスタイルや業務内容を踏まえてレイアウトを考えることが大切です。スムーズに作業が行える動線をデザインすることはもちろん、さまざまな感染症が流行するリスクを考慮したうえで、オフィスの見直しを図る必要があります。
関連記事:オフィスレイアウトの基本やデスク配置パターンを解説【最新事例20選も紹介】
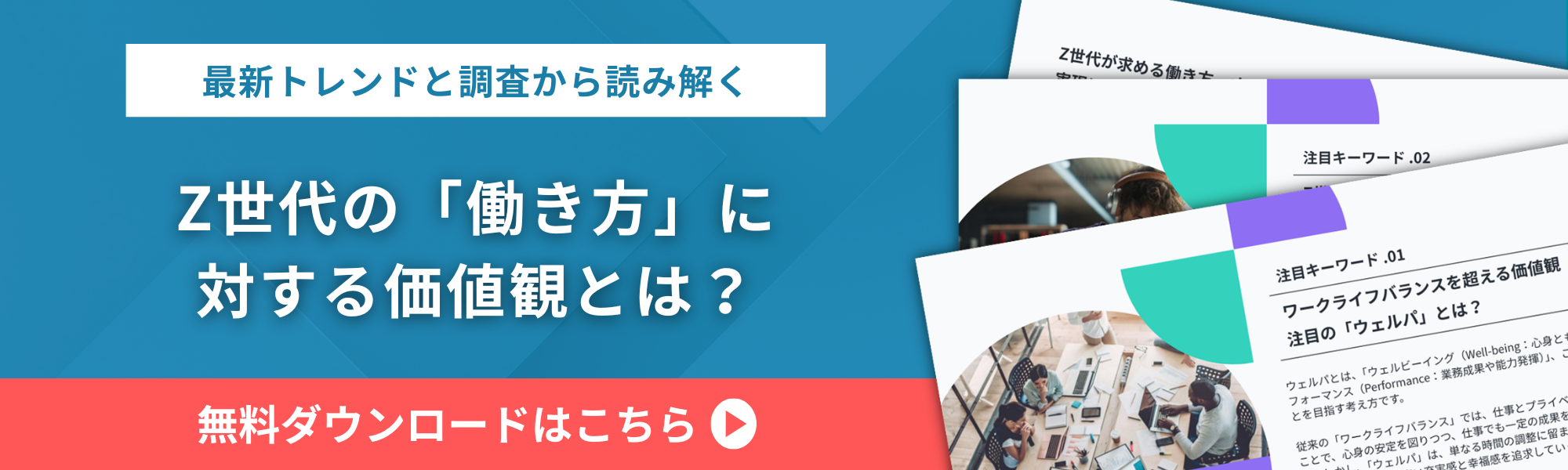
まとめ
新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に移行されたことが転換点となり、オフィス回帰にシフトチェンジする企業が増えました。オフィス回帰には、イノベーション創出やコミュニケーション促進といったメリットがある一方で、テレワークの継続を望む従業員も少なくありません。
丹青社は、多様な業界の空間づくりで培ったノウハウを活かし、柔軟かつ的確なオフィス空間をご提案します。現在のオフィスに課題を持つ方は、ぜひ丹青社へご相談ください。

この記事を書いた人

株式会社丹青社
「こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル」として、店舗などの商業空間、博物館などの文化空間、展示会などのイベント空間等、人が行き交うさまざまな社会交流空間づくりの課題解決をおこなっています。

この記事を書いた人
株式会社丹青社