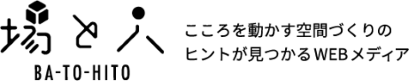SHARE
SHARE
OAフロア化するメリットや種類、選ぶときのポイントを解説
ワークプレイス |
オフィスの電話線やLANケーブルをすっきりさせたいなら、OAフロア化を検討しましょう。この記事では、OAフロアの基本情報や導入するメリット、フロアの種類や選ぶときのポイントを解説します。さらに、信頼できる製品の指標やOAフロア化の流れなど、OAフロア化するために役立つ情報を紹介するので、参考にしてください。
資料「オフィスレイアウトの基本の教科書」を無料でダウンロードする
目次
OAフロアとは
OAフロアとは、電話線やLANケーブルなどの配線を収納するために設けられた二重床のことです。床にパネルを設置することで、床とパネルの間に隙間を作り、その空間に配線を通す仕組みになっています。配線を見えないように収納できるOAフロアには、さまざまなメリットがあるため、ぜひ導入を検討しましょう。

OAフロア化するメリット

OAフロア化するメリットは以下の5つです。
オフィスの見栄えが良くなる
床の上に電話線やLANケーブルが露出していると、オフィスの見栄えが悪くなります。OAフロア化することで、床の上の配線をなくせるため、デザインやインテリアを重視したオフィス作りが可能です。
安全性が保てる
床の上の配線をそのままにしておくと、配線に足を引っかけて転ぶ危険性があるでしょう。配線が床下に収納されることで、足元の環境が快適になり、従業員の安全性が保てます。
人の通行や椅子の移動が自由になる
配線を床下に収納できると、従業員は配線を気にすることなくスムーズに動き回れるため、安全かつ快適に仕事ができます。人だけでなく椅子の移動も自由になり、コミュニケーション活性化にもつながるでしょう。
断線リスクの軽減
配線につまずくと、従業員がケガをするだけでなく、通信障害を引き起こすリスクがあります。ケーブルやコードが断線した場合には、重要なデータを損失する危険性がありますが、OAフロア化することでリスクを軽減できます。
掃除がしやすくなる
OAフロア化し、床上が整理されると、掃除がしやすくなるのもメリットです。床の上に配線があると、掃除できる範囲が限られてしまいます。コードやケーブルの束はホコリが溜まりやすく、きれいに保つことが難しいですが、OAフロア化することで改善できます。
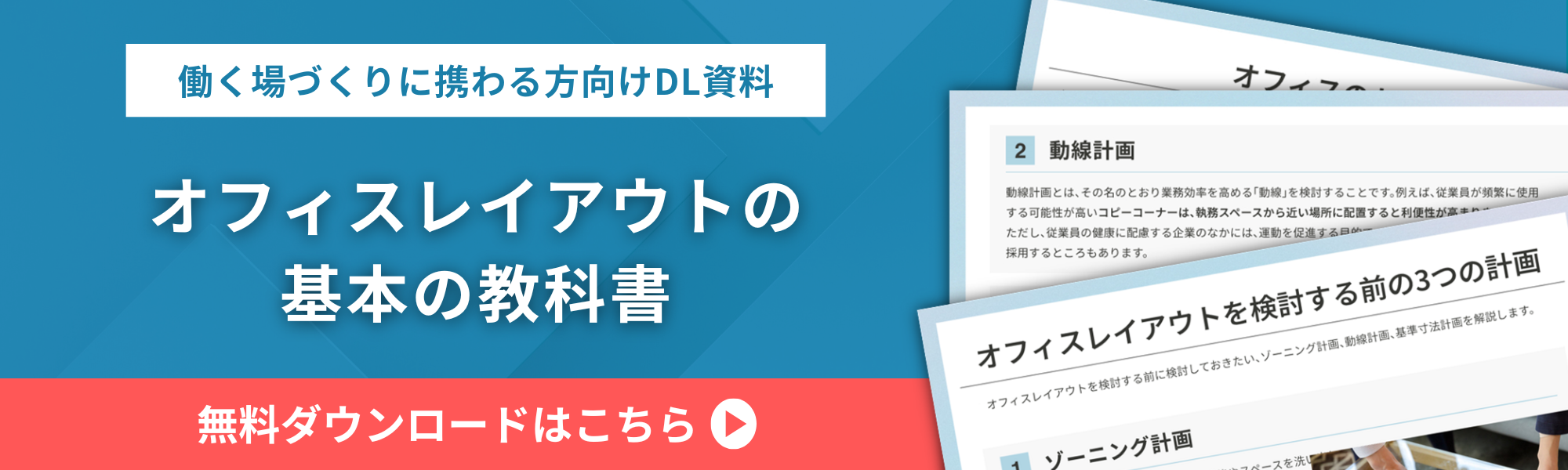
OAフロアの種類

OAフロアの主な種類は以下の3つです。
置敷式簡易OAフロア
「置敷式簡易OAフロア」とは、樹脂やプラスチック製のシートに脚が付いたフロアパネルのことです。脚があることで床面との間に空間が生まれ、配線を通すことができます。短時間で施行ができ、床にビスを打つ必要がないので、建物を傷つけないで済みます。しかし、高さ調整ができないので、フロアの床が水平でないと施工できません。
置敷式溝配線OAフロア
「置敷式溝配線OAフロア」は、配線するための溝がマトリクス状になるように設計されているタイプのOAフロアです。素材はコンクリートのことが多く、小規模~中規模程度のオフィスで導入されるケースが多くあります。配線変更がしやすく安定性があり、歩行感が良い点がメリットです。しかし、配線容量が少ないため、サーバールームや大規模オフィスには物足りないでしょう。
床高調整式フロア
「床高調整式フロア」は、スチールやコンクリートなどの頑丈な素材で作られたシートに、脚が付いたフロアシートです。現地で高さを調整し、支柱を固定した上にフロアパネルを載せて施行を行います。支柱が床に固定されているため、耐震性に優れている点が魅力です。しかし、多くの施工時間が必要であり、コストがかかる傾向があります。
OAフロアを選ぶときのポイント

OAフロアの選択肢は複数あるため、どれを選べば良いか悩んでしまうものです。ここからは、OAフロアを選ぶときのポイントを解説します。
費用
OAフロアの種類で費用は異なるため、費用から種類を選ぶのも手段のひとつです。支柱タイプは現地での調整が必要になるため、置式タイプと比較すると高くなる傾向があります。そのため、コストをかけたくないのであれば、置式タイプがおすすめです。しかし、床の状態が悪い場合は、支柱タイプが好ましいです。
施行期間
OAフロア化する際は、施工期間も重要です。OAフロア化をするにはオフィスを空ける必要があるため、空ける期間は業務を行ううえで支障になるでしょう。例えば、200平方メートルのオフィスの場合、置敷タイプのOAフロアは約1日、支柱タイプは約3日が施工の目安となります。ただし、オフィスの状況や条件によって施工時間が変動することがあるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
OA機器の数
OA機器の数も、OAフロア化の種類を選ぶ際に重要です。多くのケーブルの設置が必要な場合は、床下の空間を活用できる支柱タイプが良いでしょう。無線LANを導入していたり、固定電話の数が少なかったりするなら、配線量が少ないタイプでも対応可能です。OA機器は現状の数だけを考えるのではなく、将来を見据えて検討しましょう。
オフィスの広さ
OAフロアは面積に比例して費用が発生します。フロアが広い場合は、サーバーラックや書庫が必要になるケースが一般的です。そのため、広いオフィスをOAフロア化するなら、設備費用はやや高いものの、床高調節式のOAフロアをおすすめします。
関連記事:オフィスレイアウトの基本やデスク配置パターンを解説【最新事例20選も紹介】
耐荷重
OAフロアは強度が十分なものを選ぶ必要があるため、耐荷重にも注目しましょう。耐荷重とは、物体がどれだけの重さに耐えられるかを表す数値です。
3000Nの場合、1平方メートルあたり約300kg、5000Nの場合は約500kgの荷重がかかります。耐荷重は素材やタイプによって異なり、置敷タイプ(樹脂製)は約3000N、支柱タイプ(スチール製)は約5000Nが目安です。
材質
OAフロアは材質によって特徴があり、大規模なオフィスや、大型コンピューターを使用する場所には、強度面や耐久性から見て金属製が適しています。一般的なオフィスの場合は、樹脂製でも充分なパフォーマンスが期待できます。材質については、次に詳しく解説するので、各特徴を理解するための参考にしてください。
資料「オフィスレイアウトの基本の教科書」を無料でダウンロードする
OAフロアの材質
OAフロアの材質は主に以下の3つです。
樹脂製
レイアウト変更が多いオフィスであれば、樹脂製がおすすめです。樹脂製は接着剤やビスを打たないため、建物への負担を最小限に抑えられます。金属やコンクリート製よりも軽量で安価なので、OAフロアを簡単に設置できます。
金属製
金属製はアルミ製やスチール製などが多く、どちらも強度が高くてシートの上を歩いても違和感がない点が魅力です。アルミは非磁性体の金属であるため、サーバールームや実験室などの環境に適しています。一方、スチールは強度が高く歩行しやすい特徴がありますが、磁石に反応する性質があるため、精密機械が多く設置されるフロアにはあまり適していません。
コンクリート製
コンクリート製はしっかりしたシートのため、設置後もフロアが歩きづらくなりません。また、メンテナンスなしで長く使用でき、電子機器の誤作動や通信不良によるノイズ障害を防ぐことができます。

信頼できる製品を見極める指標

OAフロアを選ぶときには、2019年に新しくできた「JAFA性能評価認証制度」を参考にしましょう。「JAFA性能評価認証制度」はOAフロアの性能認証制度で、性能に関する表示方法を明確にすることによって、ユーザーの製品選択の利便性と、製品の信頼性向上を目的としています。
耐荷重や耐衝撃、帯電性などの試験を行い、基準に満たしている商品に「JAFA認証マーク」が表示されています。商品を選ぶ際は「JAFA認証マーク」を確認することで、信頼できる製品なのか把握できるでしょう。
JAFA性能評価認証品開発メーカー
ここでは、JAFA性能評価認証品開発メーカーと商品名を紹介します。
共同カイテック株式会社のOAフロアは、オフィスビルや官公庁、学校、病院などに使用されており、豊富な納品実績があります。高い耐久性をもつ安心の10年保証製品である「ネットワークフロア40」でJAFA性能評価認証品を取得済みです。
センクシア株式会社は、フリーアクセスフロアが主力商品で、さまざまなフロアを取り扱っています。JAFA性能評価認証品である「インナースチール(IS500N)」は、軽量・置敷全面配線方式で、リニューアルに最適です。
株式会社イノアック住環境は、国内外の特許を数多く取得しています。JAFA規格適合品は「NP 3000Nシリーズ」は、置敷きタイプ特有のスピーディーな施工が可能です。
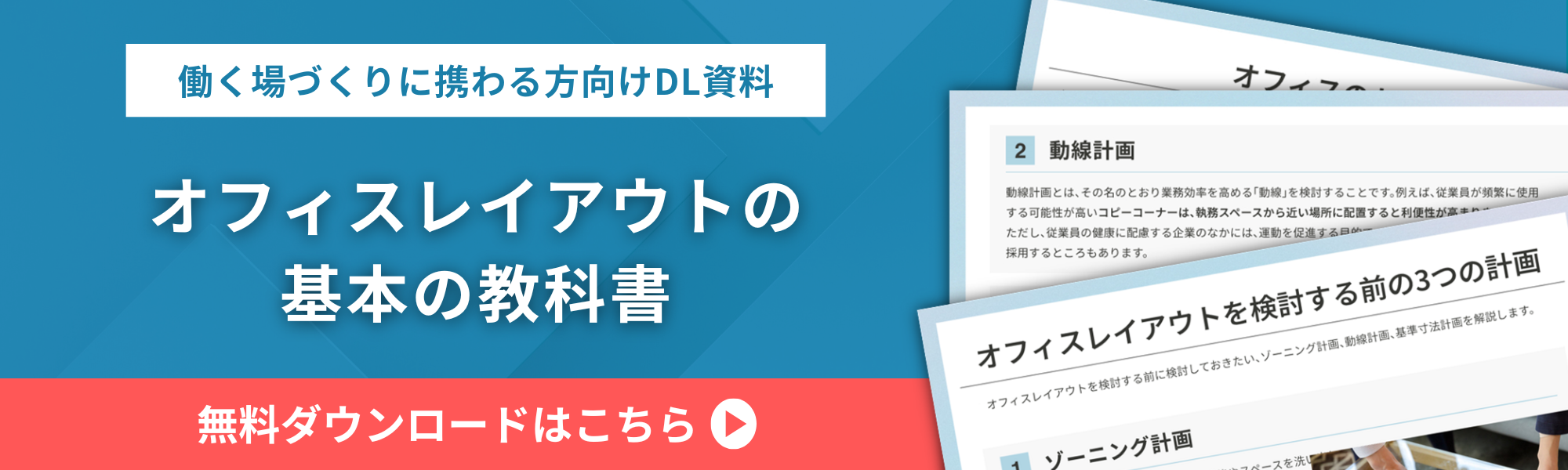
OAフロア化する流れ
ここからは、OAフロア化する流れを置敷タイプと支柱タイプにわけて簡単に説明します。
置敷タイプ
置敷タイプでOAフロア化するには、まず設置場所の床の掃除を行います。その後、躯体床のガタつきが影響しないように、クッションシートを敷きます。支柱タイプではクッションシートは敷きません。次に置敷タイプのOAフロアを並べ、必要に応じてスロープなどを設置し、最後に仕上げ材を敷いて施工完了です。
支柱タイプ
支柱タイプの施工も、まずは設置場所の床を清掃することから始めます。支柱タイプは現場で高さの調整が可能であり、支柱を使って高さを調整する点が置敷タイプとの大きな違いです。高さを調整した後、支柱の上にパネルを取り付け、必要に応じてスロープなどを設置します。最後に仕上げ材を敷いて、施工が完了します。
支柱タイプの際も、まずは設置場所の床掃除から始めます。支柱タイプは現場で高さの調整が可能であり、支柱を使って高さを調整する点が置敷タイプとの大きな違いです。調整後、支柱の上にパネル部分の取り付けをして、必要に応じてスロープなどを設置し、最後に仕上げ材を敷いて施工完了です。
OAフロアの仕上げ材はタイルカーペットがおすすめ
OAフロアの設置後は表面に仕上げ材を施工する必要があり、OAフロアの仕上げ材にはタイルカーペットをおすすめします。なぜなら、タイルカーペットを1枚めくるだけで配線にアクセスできるため、配線の変更や増設が便利だからです。また、タイルカーペットの表面は糸状の素材でできており、柔らかい印象を与えてくれる点もおすすめの理由です。
資料「オフィスレイアウトの基本の教科書」を無料でダウンロードする
OAフロア化する際の注意点

OAフロア化する際の注意点は以下の3つです。
高さ調整
OAフロアは二重床にするため高さ調整が必要です。施工前に既存の床を撤去し、コンクリート躯体を露出させたうえで設置を行います。
高さ設定を誤ってしまうと、オフィスに段差ができたり、施工状況によってはドアの開閉に支障をきたしたりする可能性があります。そのため、ドア付近にはOAフロアの設置は避け、スロープを設けるなどの工夫をしましょう。
ケーブル火災対策
ケーブルのつなぎ目にホコリが溜まってしまうと、火災のリスクになります。OAフロアの床下は、配線を適切に管理しないと火災などのトラブルの原因になるので注意が必要です。特に置敷タイプの場合は樹脂製なので、発火の影響が大きいといえます。
このようなトラブルを防止するために、国は「電気設備に関する技術基準を定める省令」を定めているので確認してみましょう。
音対策
音対策の可否は、選定や施工のポイントです。OAフロアの二重床は空洞ができるため、床上で発生した衝撃音を増幅させてしまい、階下に響く原因となります。音がひどいとクレームの原因となり、企業イメージが悪くなることもあるでしょう。そのため、歩行音や衝撃音を階下に響かせないように、騒音対策にも注意が必要です。
関連記事:オフィス環境は「音」の管理が大事!音問題の原因や対策方法などを徹底解説
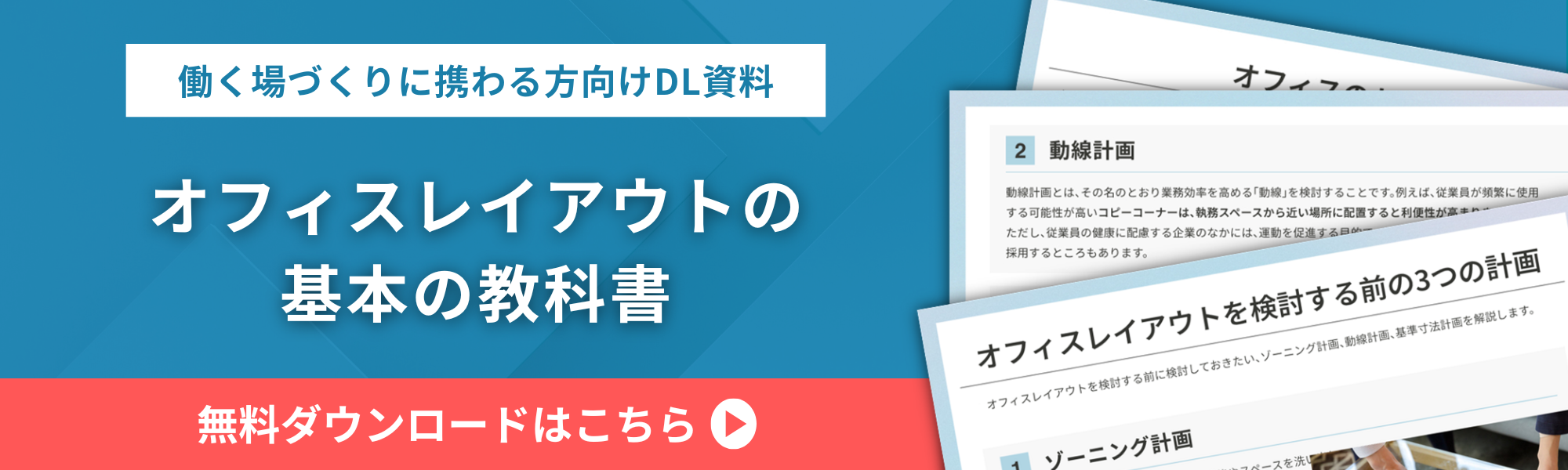
まとめ
OAフロア化はオフィスの見栄えが良くなるだけでなく、従業員の安全性保持や、断線リスクの軽減が可能です。OAフロアにはいくつかの種類があるため、オフィス環境に適したものを選びましょう。どのOAフロアを選べば良いのか悩むときは、本記事で紹介したポイントを参考にしてください。費用も大切ですが、OAフロアは長く使うものなので、信頼できる製品を選ぶことをおすすめします。
丹青社は、多様な業界の空間づくりで培ったノウハウを活かし、柔軟かつ的確なオフィス空間をご提案します。現在のオフィスに課題を持つ方は、ぜひ丹青社へご相談ください。

この記事を書いた人

株式会社丹青社
「こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル」として、店舗などの商業空間、博物館などの文化空間、展示会などのイベント空間等、人が行き交うさまざまな社会交流空間づくりの課題解決をおこなっています。

この記事を書いた人
株式会社丹青社